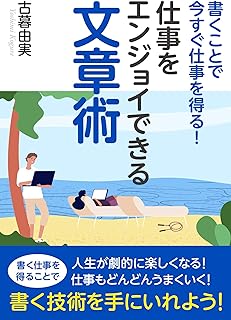【ブログ新規追加232回】

1月4日 朝9時の月。
下弦の月
下弦は6時間進んでいて、0時にのぼり12時に沈む。そのため深夜過ぎや未明に見やすい。夜浅くに西の空に見える上弦の月は、弦の部分が上に見える。(Wikipediaより)
今朝の月は、澄み切った空気のせいか、くっきりと撮れた。
☆彡
さて、2021年は「ノーストレス」を目指すことを決めて眠りについた12月31日。ベートーヴェン交響曲「第9番」の最後はうつらうつらとしながら、2020年にまみれたストレスのアレコレを反芻した。
身体の具合や人間関係や家計など、小さなわたしを苦しめるストレスはいくらでも思い出せるし、そのどれもが場当たり的な対処で乗り切ったものばかりだ。
中でも一番堪えたストレスは、「新型コロナウイルス感染防止対策からの緊急事態宣言発出」だった。
4月~5月のこと。
仕事に出られない・・・はじめての経験。それが、こんなに不安な気持ちにさせるものなのか。2か月の間、片頭痛や胃痛・腹痛などストレスの過大な影響を否応なしに受けてしまった。
そこから、今までのような希望的観測じみた浅い考えは、何一つストレスの解決にはならないという事実が分かった。
自分の浅い思考を立て直すには、巷のビジネス本などまったく役に立たない。永久不滅と言われる哲学や、絶望から這い上がった偉人のエッセイを貪り読んだ自粛期間だった。
それは、このブログでもまったく紹介はしなかった。わたし自身の咀嚼があまりすすまなかったのが一番の原因だ。
やっと、まとまった感じなので、この一冊を紹介しよう。
お正月を代表する箏の名曲『春の海』
作曲者として有名な盲目の箏曲家・宮城道雄氏の随筆集。(文春文庫)
日々の出来事や旅行、季節の移ろいや芸道について、盲目であるからこそ掴める奇跡の音。
毎日、耳にするすべての音を文字に起こし、文章を家族に口述筆記してもらい作品に仕上げた。日々の何気ないことから、こんな悲惨な出来事まで。
タンスの角に目をぶつけてしまい、眼球を潰してしまったので、それを取り出す手術を受ける著者は、自分の眼球を触らせてもらい、その感触までも文章にしている。
「まるで、大きな熟した葡萄が潰れた・・・」など。恐るべしだ。
内田百閒をはじめとする友人たちとの交流も語られ、盲目だから人生が楽しめないか?というとそんなことはまったくない!と豪語する著者に始終圧倒され続ける。
とにかく、その語り口から素直でおしゃれで意気揚々とした人物像が見えかくれする。
著者はもちろん邦楽への親しみも増していくなかで、ラベルやドビュッシーの現代ピアノ曲に影響されていく。
また、日常や旅先の出来事などを描いたものには、見る夢も「全く声ばかり」という、音と触覚だけの世界を文章にしたためた、類を見ない傑作エッセイ集だ。
音楽家として、数々の演奏会へ出向く道雄氏だが、ある日、ヴァイオリンの演奏会に赴いた幸福な一夜を辿る「メニューヒンに魅せられて」がわたしは大好き。
☆彡

と、この本が一番、当時のわたしの心境に見合った一冊だった。
「見えないから」ではなく、「見えないからこそ」最高の人生を手に入れたとまで書かれていた。
わずか、9歳で全盲となった宮城道雄氏
子どもの頃は見えていた目が、段々見えなくなることの恐怖や絶望感は、計り知れない。
翻って、現在、わたしたちが向き合いざるを得ない、新型コロナウイルスの脅威。
たかがコロナとはまったく言えないが、しかし、されどコロナだろう。
自分の置かれている状態を嘆いても、腐っても何ひとつ進展はない。
そんなストレスも、自分の謙虚なる気持ちに従って、淡々と新しい一年を越し続けて行くのだ。
浅い評論家からは、距離を取って、地味に強かにやって行こう。