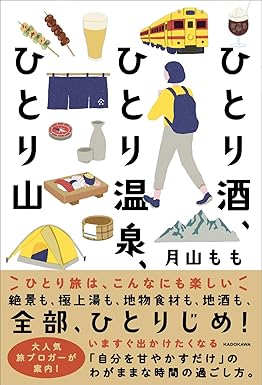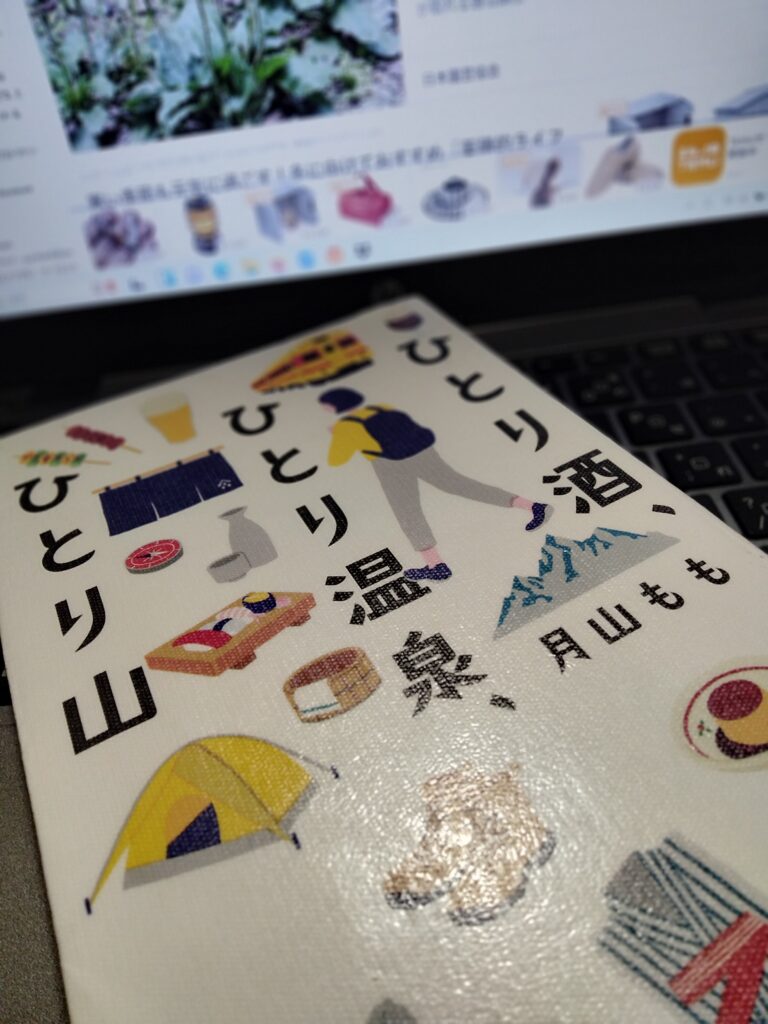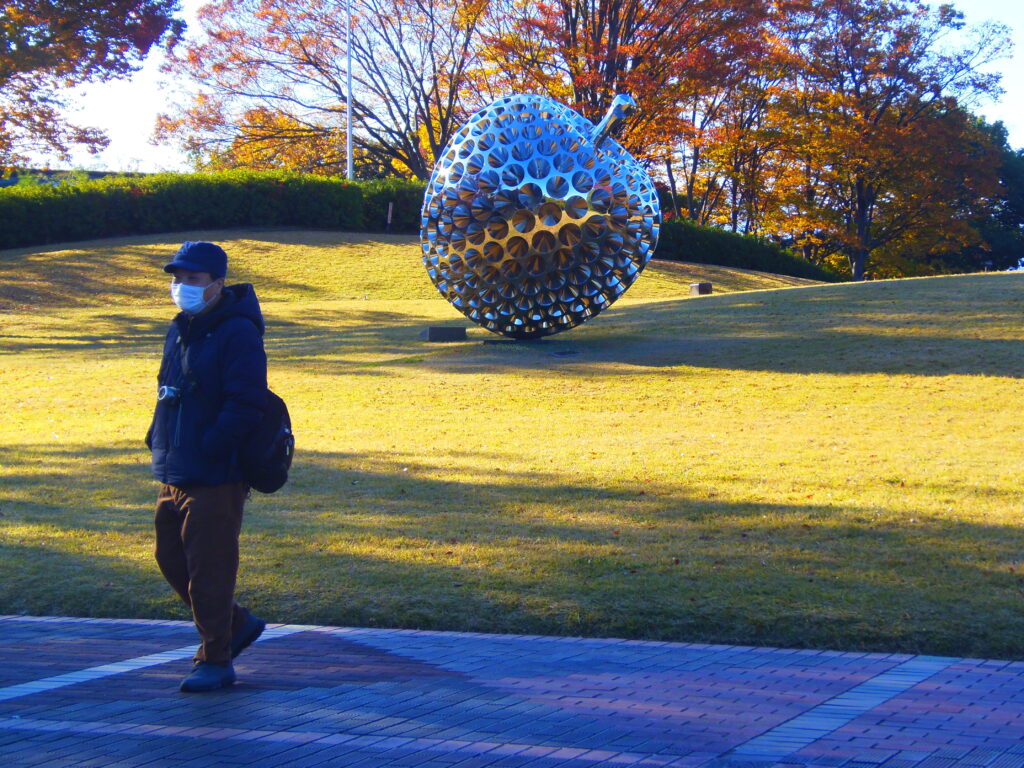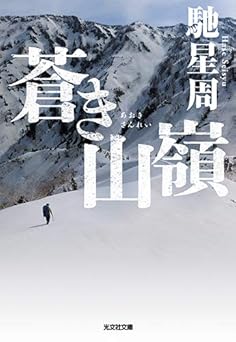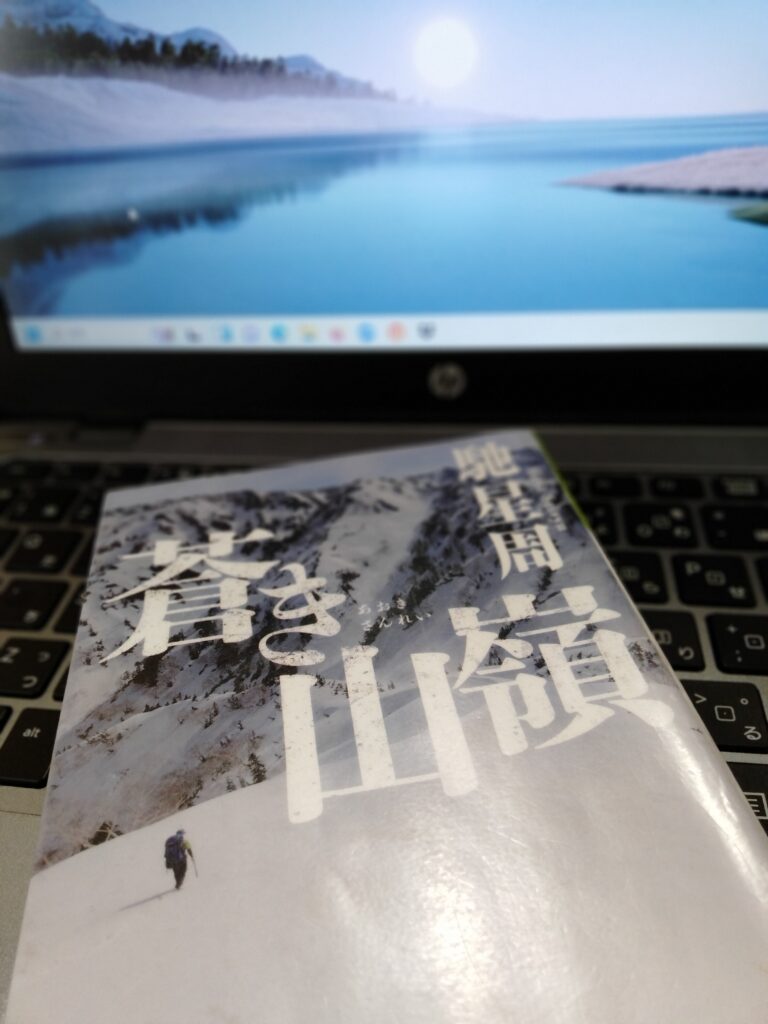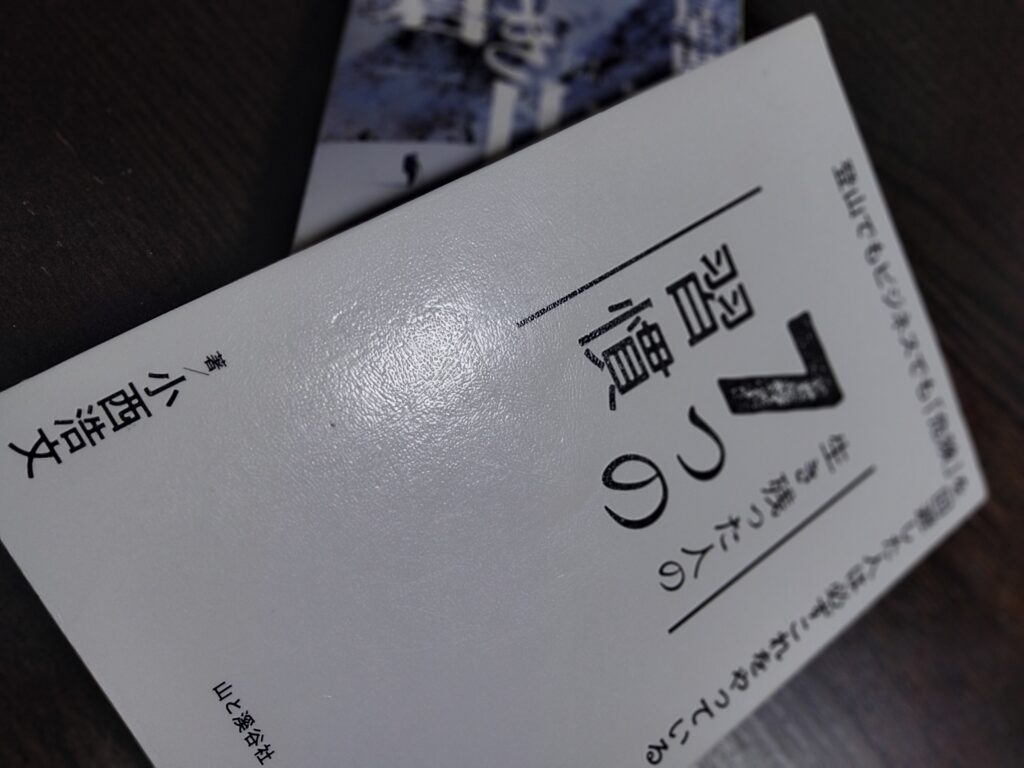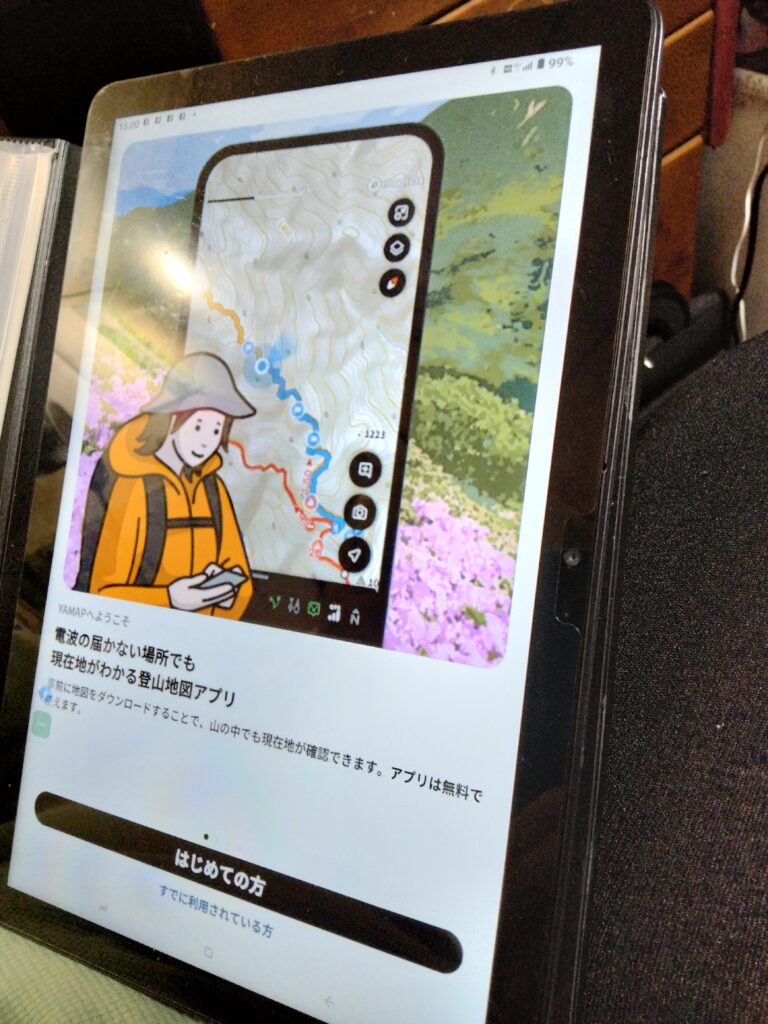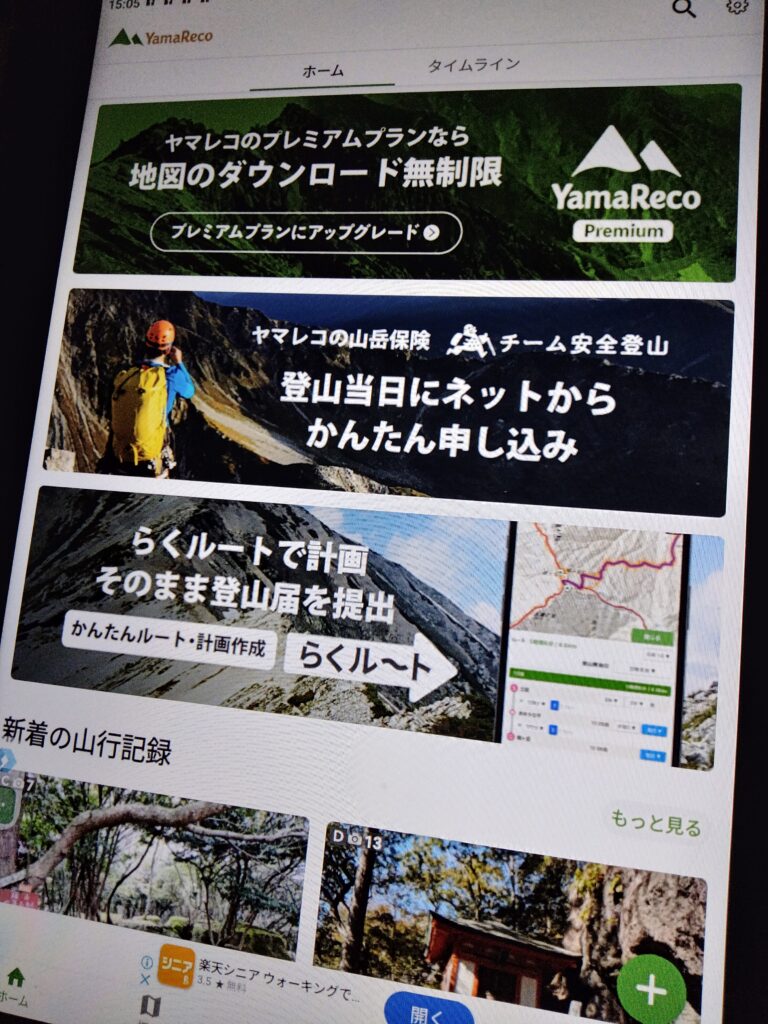【ブログ新規追加1279回】

※能率手帳のNOLTYが今年も素敵なライフログ手帳を販売中。
ライフログってご存じ?
いわゆる、日記のことなんだけど、言い方を変えると何だかとってもアクティブじゃない?
ライフログの定義を調べてポイントを箇条書きにした。
◆ライフログとは? 自分を知るための記録である。
◆ライフログの活用で「本当に必要なもの」が見えてくる。
◆自分にとって「必要なもの」を見極めるためのライフログの書き方1~3
▼ステップ1:興味や関心を自由に書き出す。
▼ステップ2:後から振り返る習慣を持つ。
▼ステップ3:好きなことと嫌いなことを分類する。
◆ライフログで「必要なもの」を見極めることでの副次的効果を得る。
▼無駄な出費の見直し。
▼優先順位を決めた支出。
▼節約と貯蓄のモチベーションアップ。
こんなところだろうか?
積み重ねてきた人生の棚卸しにぴったりな「ライフログ時間」だってことだわね。
ライフログをスタートさせるのに年末年始が丁度いい。
「年末年始にぴったりの行事」にしてみたらどうだろう?
スケジュール帳とは違う視点で手帳を使いこなすのよ。
これからの時間をどう過ごすかを考え直す「絶好のタイミング」だと思うし。
わたしの毎年の棚卸しは、だいたい12月中に済ませておいて、それを見返すのは、お正月三が日なの(笑)
わたしの、これからはじまる「あれやこれや」がいっぱい詰まった手帳を見返しながら1年を占う。こんな楽しい時間はないかも!
さて、次は、楽しい時間を彩る手帳の話をしよう。
日本能率協会がバックアップする「能率手帳」通称:NOLTYが、ライフログを楽しく行い、素敵な手帳時間を過ごしてもらえるような、アイテムが種々豊富に売り出されている。
NOLTYの唱える「素敵な時間」とは?
素敵な手帳商品とともに、ライフログの紹介文はこちら(ちょっと詩みたいだね)
~出来事を書く。気持ちを書く。何でも書く。塗ったり、貼ったり。時には見返してみる。毎日を、人生を、そんな時間でもっと、たのしくなる。さあ、ライフログをはじめよう~
今では、素敵な手帳にあれこれと書いて行くのが日記の定番だそう。
何だか、「スケジュールいっぱい書き込む」だけじゃなくて、あれも、これも自由に書き込むとかいうがイマドキなんだと、改めて知った。
だから、スケジュール帳とかいう名前はあれど、おしゃれな雰囲気のあるライフログ手帳と呼び名も変わったんだ。
NOLTYは、書店や文具雑貨店においてある、ちょっと高価な手帳だ。
今日見たのは、だいたい1500円前後に素敵なカバー付きが多かった。まあ、1年みっちりと、一緒に過ごすんだから、安い!ものかもね。
どうぞ、NOLTYに興味のある方は探してみてね♪

★★★
ライフログ関連の書籍も紹介しよう。
『ねこねこさんの バレットジャーナル活用術』~シンプルなのに驚くほどうまくいく!~ねこねこ・著(エムディエヌコーポレーション)
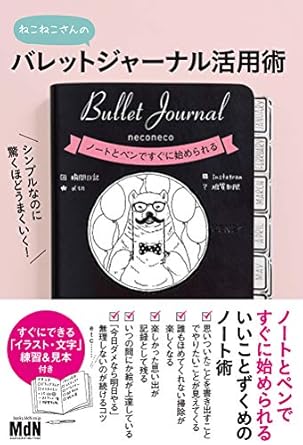
簡単レビュー
ノートとペンがあればすぐにでもはじめられる、
話題の手帳術バレットジャーナル!
バレットジャーナル手帳術を覚えれば、白紙のノートが自分仕様の手帳に変身。書くのがどんどん楽しくなる!
可愛いバレットジャーナルを始めたいと思っている人必見。
ねこねこさんに学ぶ、無理をしないで毎日が充実&楽しくなるヒントが満載の一冊だ。
本書では、バレットジャーナルを活用しているネットでも人気のねこねこさん(@88necoco)に、
スケジュール管理、TODO管理はもちろん、ダイエットノート、買い物リスト、アイディアメモ、未来ログなど
さまざまな用途に使えるバレットジャーナルの作り方を伝授してもらった。
バレットジャーナルの基本から活用メソッドを解説。
後半ではイラストが描けない人でもすぐに使える、練習ページを用意。
バレットジャーナルに使えるイラストや文字の描き方など解説している。
〈いいことずくめのノート術〉
・思いついたことを書き出すことでやりたいことが見えてくる
・明日の朝起きるのが楽しみになる
・誰もほめてくれない掃除が楽しくなる
・楽しかった思い出が記録として残る
・いつの間にか絵が上達している
・「今日ダメなら明日やる」無理しないのが続けるコツ etc.
さあ、お好きな手帳に思う存分書きまくって、たくさん叶えてみよう!
それでは、また!
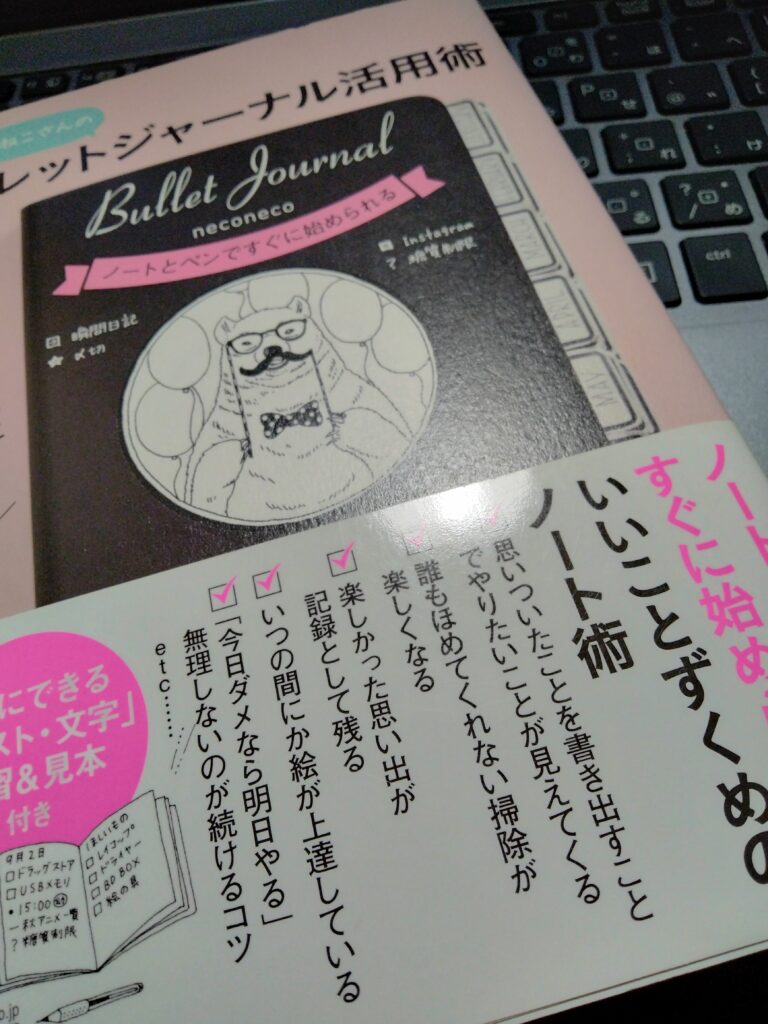
---------------------------------------------旧記事更新187
『SunTAMA Style』2020年12月4日記事
『SunTAMA Style』2021年12月4日記事
『SunTAMA Style』2022年12月4日記事
『SunTAMA Style』2023年12月4日記事
『LifeTour 21st』2015年12月4日記事
https://lifetour.blog.jp/archives/1046598334.html 「さあ!旅の準備をしよう」