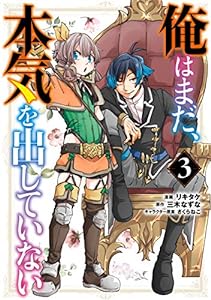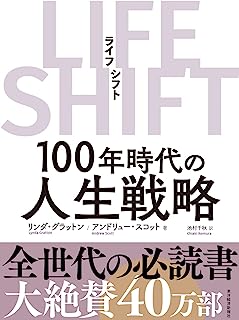【ブログ新規追加294回】

昨日、3月11日は東日本大震災から10年、ひとつの区切りを迎えた。
あの日、明け方からずっと同じTV画像(津波)が流れて、それが、いつ止むのかわからない大混乱な日々に突入した、まさに一生忘れられない日となった。
わたしは、当時、病気から仕事に復帰して1年目、まだまだ思うように身体を動させなくもどかしいながらも、やりがいと希望に満ち溢れていた頃だ。
幸いにも東京都下に住んでいたことから、直接、地震での影響を受けたのは、ガソリンが買えない、パンが買えないなどの流通がらみの案件だけだった。
昨日、あの日を思い起こしていたら、それからの10年に起こった様々な思い出が数珠つなぎとなって止まらなくなったの。
で、ネット上でも、「自分のこの10年を振り返る」という記事を目にした。
わたしも真似してみよう!と。
それでは、簡単に振り返ってみよう。
● 2011年・・・東日本大震災勃発。脳出血後1年経過。仕事復帰1年目。
● 2012年・・・営業職が肌に合う。仕事尽くめの毎日。わたしの母の介護がスタートする。
● 2013年・・・仕事・介護に追われる毎日。
● 2014年・・・息子就活成功。夫の両親の愛媛転居。
● 2015年・・・息子の転勤が決まり巣立ちを迎えた。ブログ立ち上げ。
● 2016年・・・わたしの母が亡くなる(看取りと家じまいは大変)兼業ライターをスタート。5月に電子書籍で初出版を果たす。
● 2017年・・・夫の父が亡くなる。
● 2018年・・・夫の母が亡くなる。夫の心筋梗塞発病。
● 2019年・・・夫の心臓手術が2年で6回断続的に続く。兼業ライターを辞める。元号が「令和」となる。
● 2020年・・・新型コロナウイルスが世界中で感染蔓延する。緊急事態宣言の発令、仕事・外出への自粛が2ヶ月続く。2冊目の電子書籍を出版(紙版あり)
● 2021年・・・現在に至る。

人生の区切りがたくさんあった。特に親との永遠の「別れ」が3回。この件は筆舌に尽くしがたい。
また、夫の大病もわたしにとっては、精神的にも肉体的にも経済的にも大打撃の出来事だった。
もうね、書き出しただけで疲れてしまった。
人生のクライマックスが次から次へと、まさに津波のごとく襲いかかってきたんだもの。
きっと、ほとんどの人がこのような苦難や困難に見舞われながらも、強くたくましく生き抜いていくんだろうな。
また、そうするしかないもの。
わたしにとっては厳冬の10年だった。
しかし、苦しい中にも小さな楽しみをきちんと見つけられる心の余裕が持てたのは、読書のおかげだと感じる。
多くの「表現」や「言葉」に触れて、自己肯定感を保ててこれたのだ。
これからの10年も、同じように読書を栄養の「糧」として取り入れて行く。
そして、栄養を吸い取ったあとは、ブログに紹介を残して行こう。
ブログはわたしの自分図書館だもの(笑)