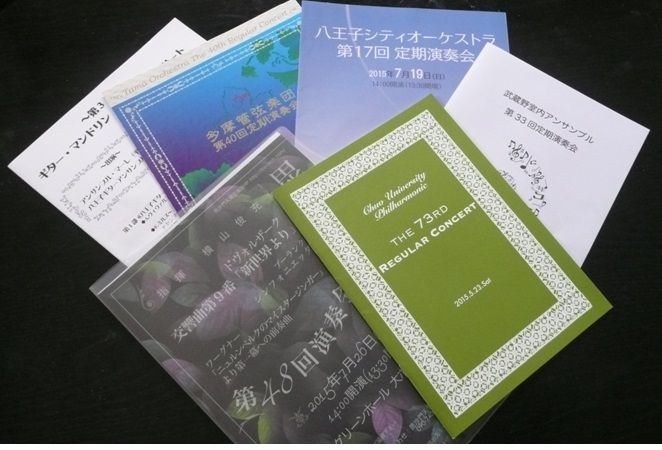【ブログ新規追加198回】

● 香港式ミルクティが好きな理由
冬が来る前に、暖房器具と冬用の飲み物を用意する。我が家の冬用とは香港式ミルクティ。
毎年、茶葉を選ぶところから始めて、練乳(エバミルク)を使うので、カップも少し、ぽってりとした可愛い器を用意する。
ミルクティには、イギリス風、インドのチャイ、香港式と大きく3つ挙げられるが、わたしが愛してやまないのは「香港式」だ。
これを飲みたくて、一昨年、真夏の香港に久しぶりに訪れた。それも弾丸で一泊(笑)
以前の香港旅のブログはこちら→「グラマラス香港」リンク先→http://lifetour.blog.jp/archives/1067491444.html
以前と違ったのは、ぽってりとした香港特有のティーカップで飲めるミルクティは、年々姿を消し、ファーストフード店、ショッピングモールのフードコートなどで紙コップでサーブされるのが、通常になっていた。
約20年前は、町の片隅の喫茶店で一杯200円程度で飲めていたお茶。可愛いぽってしたりカップで出されるミルクティ。合わせるのは焼き立てフレンチトーストやエッグタルト。
香港ペニンシュラホテルでは、夏場、ガラスの素敵なカップ&ソーサ―でサーブされていた。
紙のカップでも、あの練乳(エバミルク)のぷ~んとした甘い香りと、薫り高い茶葉の飲み心地は変わらないけど、お茶を頂く楽しみはやっぱり「器」にあるのだ。

今、コロナと中国社会情勢の厳しい中、香港には出向けないが、規制緩和されたら、あの可愛いぽってり系のティーカップを探しに香港に行きたいと願っている。
● 香港式ミルクティ~レシピ
【材料】1人分
- 濃い目の紅茶 1杯
- 練乳(エバミルク) 大さじ1~2
- 砂糖 やや多め(お好みで)
【作り方】
鍋で濃い目に煮出した紅茶に、砂糖と練乳(エバミルク)を入れてよくかき混ぜれば出来上がり。
※ わたしはアッサムという茶葉を多めに煮だして使っている。ミルクに良く合う茶葉だと香港のお茶専門店で聞いてから、アッサム一択だ。どっしりとした深み、独特の甘みがある茶葉。
※ 砂糖の量もお好みで。練乳(エバミルク)を使うので、我が家では砂糖なしで飲む場合が多い。

写真;スターフェリー乗り場(尖沙咀埠頭).付近で売っていたエッグタルト。ふんわりした甘い卵がめっちゃ美味しい!(1個70円)
現地香港では砂糖多めのまったりとしたミルクティを頂く。歩き疲れた時、エアコンで体が冷えた時などはこの甘さが病みつきになる。
飛行機に乗る前にもcafeで飲んで、体の冷え対策と病みつき最後の一杯を堪能した思い出。
● 茶葉のいろいろ

秋から冬の空気が漂い始めると、お茶が美味しく感じられる。
普段は断然コーヒー派なのだが、香り高いセイロン・ティーなどをたっぷりのミルクで満たして飲む幸せ感には言い尽くせないものがある。
冬のはじまりに飲みたい紅茶の種類は「ウバ」である。
世界三大銘茶のひとつである「ウバ」は、8月の終わり頃ベストなものが収穫され、9月〜10月に新茶として出回る。
「ウバ」は、セイロンの中でも絶対的な個性のあるお茶で、独特の香りと渋みが好きな人にはとても合うと思う。
好き嫌いがはっきりするお茶かも。
季節に応じてこだわりのお茶を一茶入魂してみると面白い。
お菓子などのマリアージュも、自分ならではのチョイスで選んで見るときっと楽しいだろう。
あと、おまけに「ハーブ・ティー」のことも少し。![]()

ハーブはもともと「緑の草」を意味するラテン語の「ヘルバ」が語源と言われている。
古代エジプトなどでも薬用に利用されたことが知られている。現在の科学的に合成された薬ができる前は、中国の漢方などと同様、医療にも活用されてきた。
ハーブが注目を集め始めた理由の1つは、ほぼノンカフェインであるということ。
カフェインの多いコーヒーなど、寝る前に摂ることを懸念されていた人たちがハーブティーを飲み始めたことから広まったらしいのだ。
ハーブティーには多くの種類があるが、大きく「リフレッシュ系」と「リラックス系」に分けられる。
気分転換したい時や仕事や勉強に集中力を高めたい時は、ペパーミントやレモングラスなどリフレッシュ系のハーブを。
気分を和らげ、ゆっくりと休みたい時はリラックス系のカモミールやラベンダーがおすすめだ。