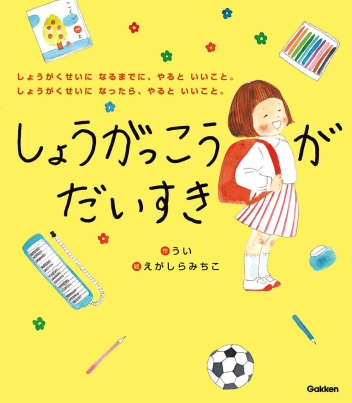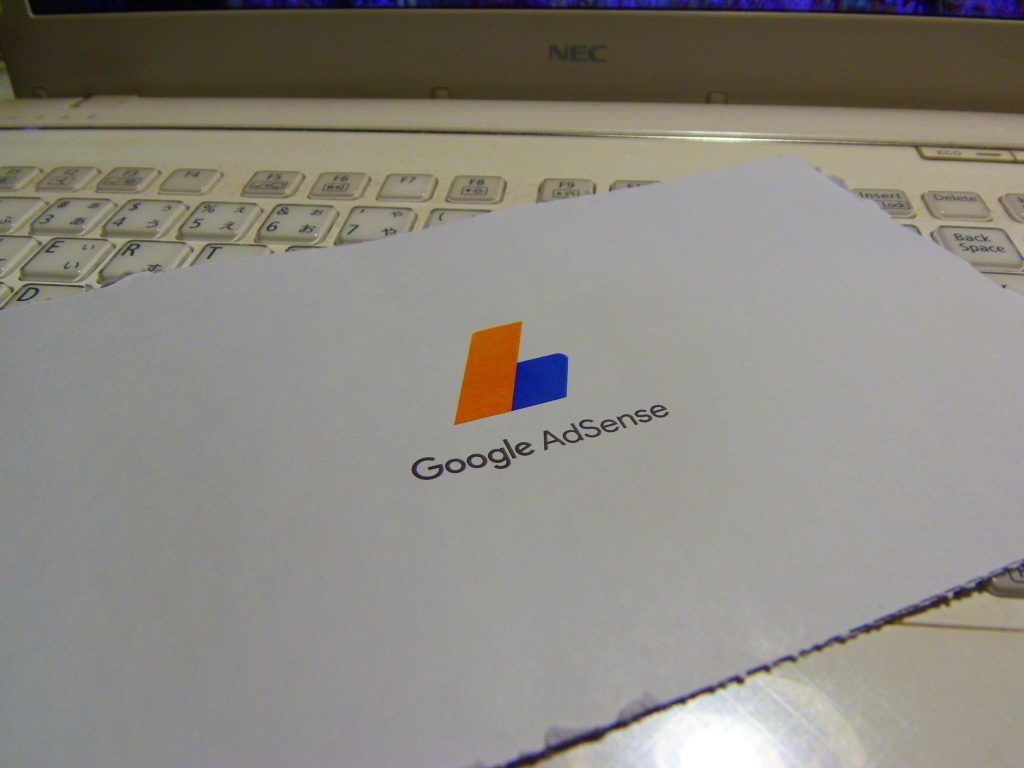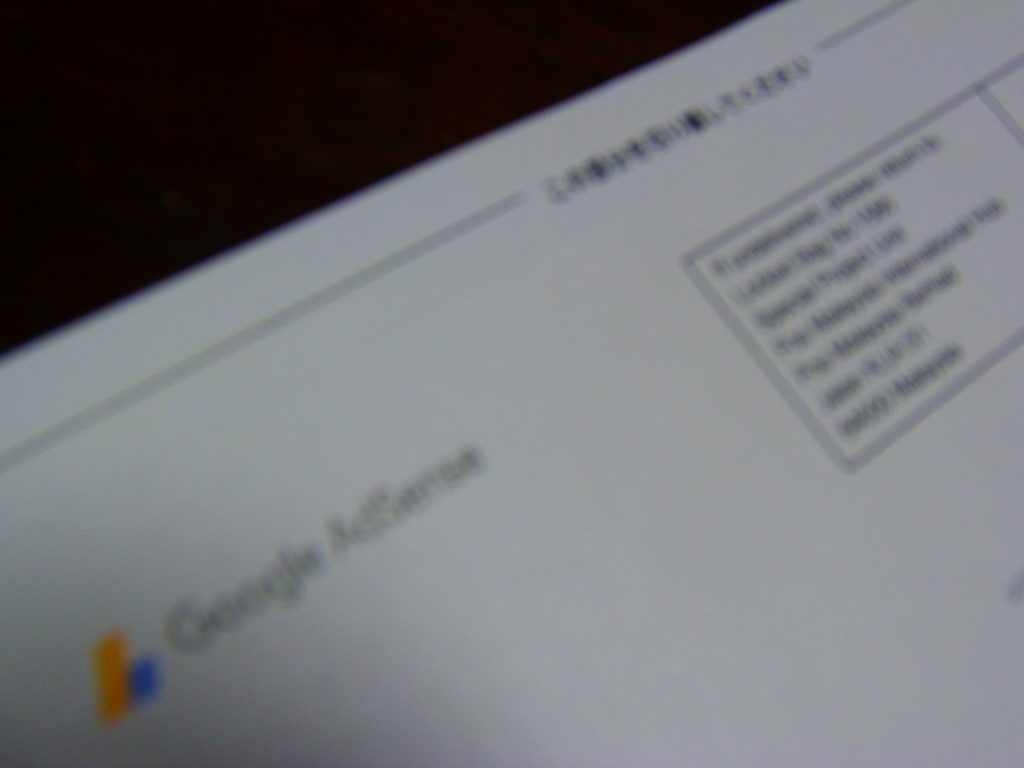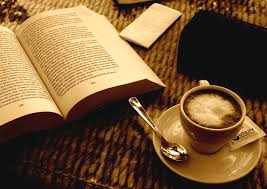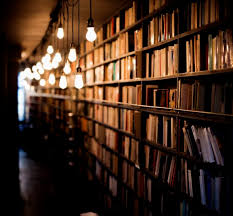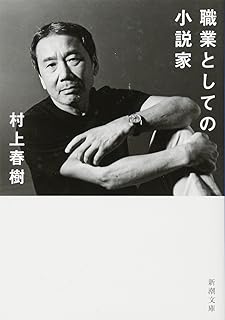【ブログ新規追加265回】

2月になって、素晴らしいお天気の日ばかり。着々と春に向かっている。
こつこつと地味な更新というルーティンが必要不可欠なブログ。
SNSは別に不定期であってもいい。第一仕事じゃないのだから。
しかし、ブログは若干の仕事モードに切り替えた2020年。仕事と見立てているから毎日書く。
春の訪れに、トレッキングや山歩きに出たくて、ソワソワな毎日だ。あれほど本気で読んでいる本も、2月に入ってからはまだ5冊程度の読了。
ただ、読書もやみくもに読了を目指してはいない。
ルーティンでもノルマでもないから、ここも外に出たい気持ちを抑えてまで無理やり詰め込もうなんていうのは絶対にしないんだ。
そんなわけで、2月はゆるゆると「好き」を詰め込んでいる真最中(笑)
☆彡
春はわたしが一番好きな季節。
しかも、今の家から低い山や丘陵地帯と自然公園まで徒歩5分。自然公園自体は、低山なのだが、その頂上の草むらに「四つ葉ばかりのクローバー」が茂る場所がある。

息子が小学生の頃通った、学童保育クラブで教わった秘密の場所。
当時、遠足で登った時、四つ葉をたくさん摘んだのよ。そこまででも、今の家から徒歩30分という危険な立地(笑)
なぜ、危険か?といえば、毎日でも行けちゃうから。四つ葉それだけで、仕事や他の用事を潰すつもりはない。
でもね。その四つ葉の場所があれから一度も見つからない。それを探しにいくハンティング欲が異常に漲ってくるの。
そして、いつかは書きたい20年越しの「四つ葉のクローバーだけが咲く丘」の短編。
わたしの書く話は基本的に「自分の経験・体験」から書く。
あまり創作を好んでいないのかもしれない。
そして、他人の疑似体験や追体験を書く事も多分、ないんじゃないかな。
どうしてないのか?これについては、またそのうちに。
☆彡
さて、
ブログの持つ習慣性の話をしよう。
以前のブログの頃にあるブロガーさんと非公開でメッセのやり取りをした。彼女はよく、書けなくなるらしいの。その時、筋トレの筋肉を思い出すという話をしていた。
わたしは、書けなくなるとか、あまりそういうことはないのだが、彼女は、書く頻度が下がり続けるとどうなるか?といえば、筋トレと同じで、ブログ筋=文章筋が弱くなってしまうのだと話していた。
ブログ筋=文章筋が弱ると、まず、書くスピードが遅くなり、アイデアが湧きにくくなる。また、無理をして書いてみても、思うような表現がスッと出てこない。
で、このループに入ると「書く意味」を見いだせなくなり、どんどん億劫になって、「もう、いいや!」と、ますます書かなくなる負の循環が待っている。
そういう時に危険な思考は、書けないくせに「きちんとした文章を書こう!」と、自分の肩に負荷をかけるのだ。そしてさらに書けなくなるのだそうだ。
そして、わたしへの質問「こんな時どーしたらいい?」と聞かれた。
とっさにわたしは、普段の自分の執筆スタイルの基本をお話しした。
それは、日記や雑文、短編小説でも、すべて、「自分が体験したエピソードだけ」で書いているのよ・・・と、話し、書くのに行き詰ったら、「自分を掘り下げてみて!体験を書いて!」と、背中を押したのだ。
☆彡
軽い日記でも、雑文でも、その内容が「本人の体験」から出て来たものだったら、ちゃんと書けないわけはないし、反対にスッと書けてしまうんじゃないかな?
体験をていねいに抽出する。コーヒーをゆっくり豆から落とすように。
~事実は小説より奇なり~だもの。
書けないからって、どこかの有名な誰かみたいな文章など真似ても仕方がない。
書けなくなった時には、ウォーミングアップかリハビリのつもりで、体験エピソードを文字にすることを目いっぱい楽しむのが一番。
書けない・・・この状況を味わい尽くそうと、話をまとめた。
わたしはずっと、この体験を書くという「自分発」思考で、書き続けてきた。
最近では、脳の回転とキーボードを打つ指の速度までも一つの回路として成り立っている(気がする・笑)
ブログの持つ習慣性の凄さを実感する毎日だ。
春浅い間に肩の力が抜けて、気がついたら
「快心の文章」が書けていたとか・・・夢だね。