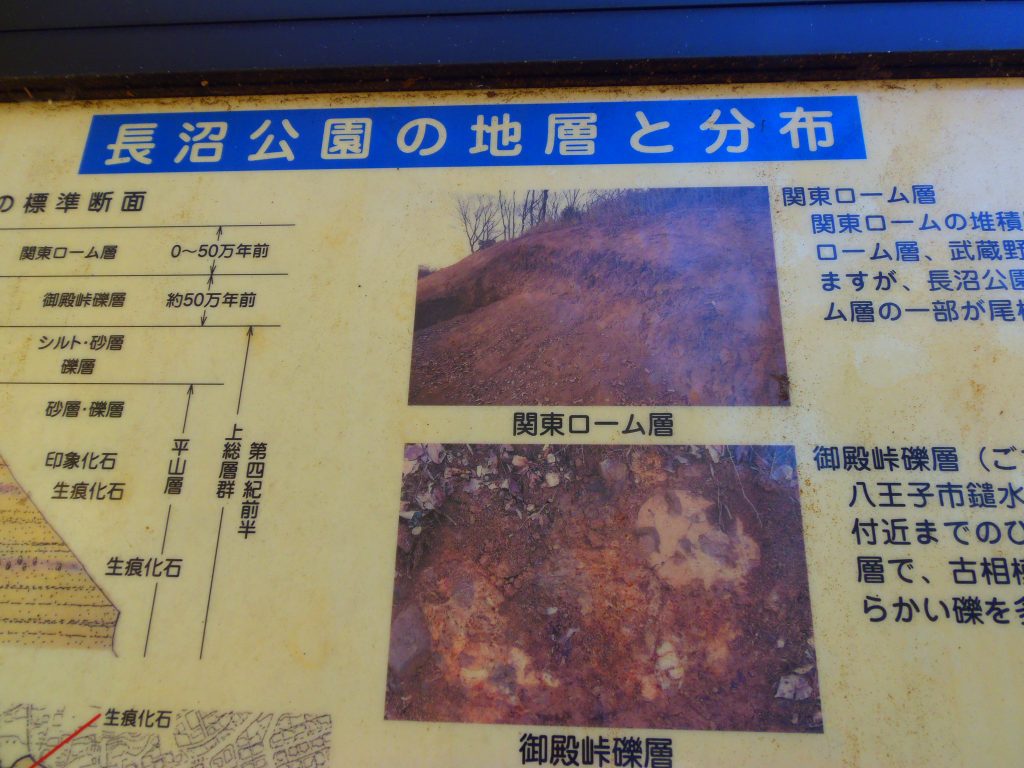【ブログ新規追加284回】


今朝、良く晴れて風も穏やか。これなら、「つどいの森」で、ディ・キャンプできそう!と、朝6時からいそいそと準備を始めた。
家から車で15分足らずの場所に、東京では、めずらしい、予約なしで無料のディ・キャンプ場がある。
ここ「つどいの森」は野営(泊まり)はできないのだが、開門朝9時~夕方5時閉門まで、晴れていれば遠くに富士山が見え、市内を見渡せる眺めのよい高台の広域芝生公園だ。
すでに1台待ち。やっぱり早めに来なくっちゃね。9時オープンではあっという間に5台入ったもん。もちろん無料P。公園全体では30Pあるけどかなり歩くの。
★
さて、わたしの趣味の基本は、低山(1000mぐらい)の山登りだから、キャンプしないで済む装備にしたいのが本音。
一方、夫は山よりもディ・キャンプがしたいという。意見が分かれたから、今回はディ・キャンプで、山登りに持って行くコーヒーや軽食を作る燃料を試すのを目的に用意をして行った。
で、「つどいの森」では、現在BBQ禁止(自粛)という案内がされていた。公園や山なら大丈夫というわけではなかった。残念。
そんなこんなで、BBQは諦めて、固形燃料でコーヒーを淹れチーズとパンを焼いて試してみた。小型バーナ―や炭火はまたの機会にしよう。


わたしは、小型バーナ―、練炭や炭火、固形燃料のそれぞれを試してみたかったんだ。実際、今日は固形燃料でコーヒーを抽出してみた。美味しいけど熱々からは程遠い。
先週、高尾山で小型バーナ―を使い「高尾そば」を茹でる動画を観た。小型バーナ―でも少々ぬるいそうだ。そばがもそもそする~~~とか、言ってた(笑)
山にはウルトラライトハイク(極端にモノを減らして登る)これで行く。低山ならではの身軽な装備に憧れている。
だから、コーヒー一杯のために重量オーバーとまでは言えなくとも小型バーナ―は必要でないのかも。
でも登った後の熱いコーヒーは最高のご褒美だから諦め切れないの。もうね。燃料関連はいつも最重要で、検証が大事なのだ。
重い荷物は絶対にイヤだし、無理だし、ホント、迷いの境地(笑)

今朝の寒さ(風が強い!)にも、完全防備して3時間のディ・キャンプを楽しんできた。その日、その日でできることが変わってくる自然の中での遊び。

きれいな眺めを存分に楽しむコロナ禍のディ・キャンプ。翌日の仕事に響かない、低装備キャンプは本当にいいストレス解消になる。
おススメよ。
「片倉つどいの森」情報先→https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/109/p011932.html