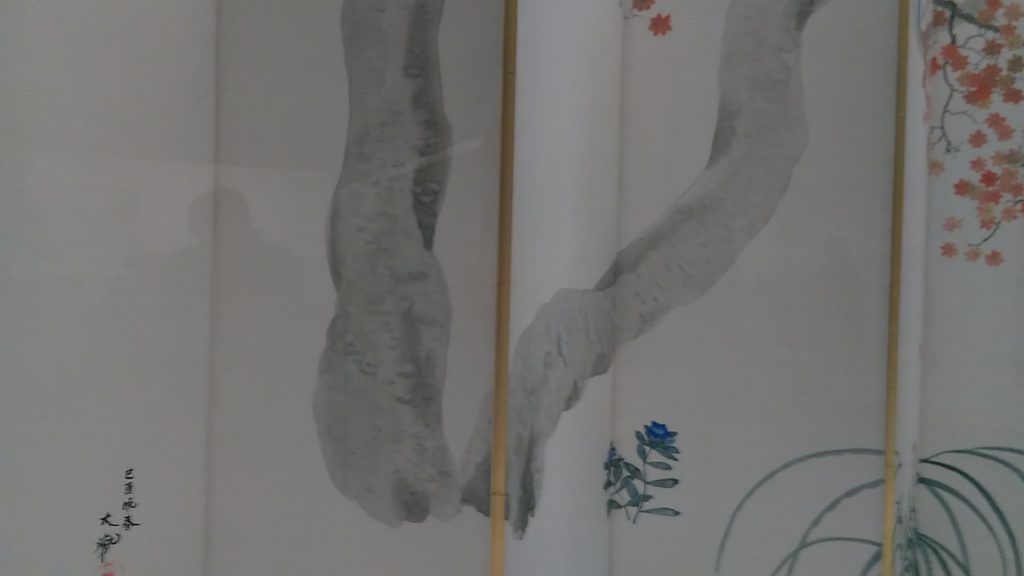【ブログ新規追加260回】

● 自分のご機嫌を取るために用意したモノ
立春を晴天で迎えた。
立春は中国では旧正月。新しい年が始まったところなんだね。
わたしも、立春に今一度、「この一年を好きなことで埋め尽くし輝くため」に小さな手帳を用意した。
今さらとかは、まったく思わない。
小さな手帳に「宝モノみたいな好き」や「欲しいモノ」や「やりたいことがら」をいっぱい書き集めて、ワクワクしながら眺めている(笑)
自分のご機嫌は、自分でしっかり取るのが大事よ。
● 自分のご機嫌を取る行動は、光輝くお花を愛でる場所に行く
といっても、この行いは、特別な場所などではない。
日頃、外営業で回っている場所に、思いがけず美しい花壇があったり、遠くに輝く山々が煙るような時期にはカメラを車に積んでおく。
そして、仕事がひと段落したら撮影をするのが、わたしの最高のボタニカルライフ。
今日は、毎月美しい花壇を作っている神奈川県相模原市の東電へ。
ここは、知的障害や肢体障害を持つ人たちが一生懸命、丹精こめて手入れをしている街の街頭花壇だ。
だいたい、毎月季節の花に植え替えられているのが驚き。
この数年の記憶では、3月はノースポールだったかな。
香りもよく、青空に映える花たちが壮観に咲き誇る。
毎月、この花壇を見ることを本当に楽しみにしてきた。
念願叶っての今日は、一期一会に期待して2枚だけ撮影してきた。

● 自分らしさを見つけて輝くためには、ちょっと視点を変えてものごとを見てみる
平凡な日常をちょっと感動的に、色鮮やかにする方法があるとすれば。
それは「エッセイを書くように街を歩く」この行いに尽きる。
よくある日常的な事柄も、エッセイの中では、まるでドラマティックな映画のワンシーンのように描けるものだ。
もし、エッセイを書いてみたいと思うなら、自分の一日を書き出してみると良いよ。
あんまりにも書くことがない・・・というわけでもないのがわかるはず。
だって、お味噌汁の具にこだわってるかもしれないし、ご飯の炊き方にこだわりがあるかも。
ご飯とお味噌汁だけでも、充分に立派な一本のエッセイが仕上がるのだ。
その平凡だけれど、美味しいご飯とお味噌汁をどう表現するか?
好きな映画のヒロインを真似て書くとか、好きな作家の文体に寄せて書くとか、
いろいろ自由に書けるのがエッセイの魅力。
私たちの身の回りにあるごく当たり前のことが、なぜエッセイになると印象的なものになるのか?
それは作家が、私達とは違う視点から日常を切り取っているからだ。
だから、わたしみたいな普通の人でも、ほんの少し視点を変えることで、いつもの風景が特別なものに変わりうるから、文章の世界は楽しいんだ。
★
パンジーやビオラは普通の園芸種。別に珍しくも何でもない。
それが、身体の不自由な人たちの「手」で愛情込めて、植えられて見事に咲き輝いている光景を、いつか写真に撮ってみたかった。
かっこをつけなくても、飾れなくても、無心に作業に没頭する彼らは充分かっこいい。
ドラマは、普通のところにあるものだ。
今年も普通の輝きをいくつ見つけられるかな。