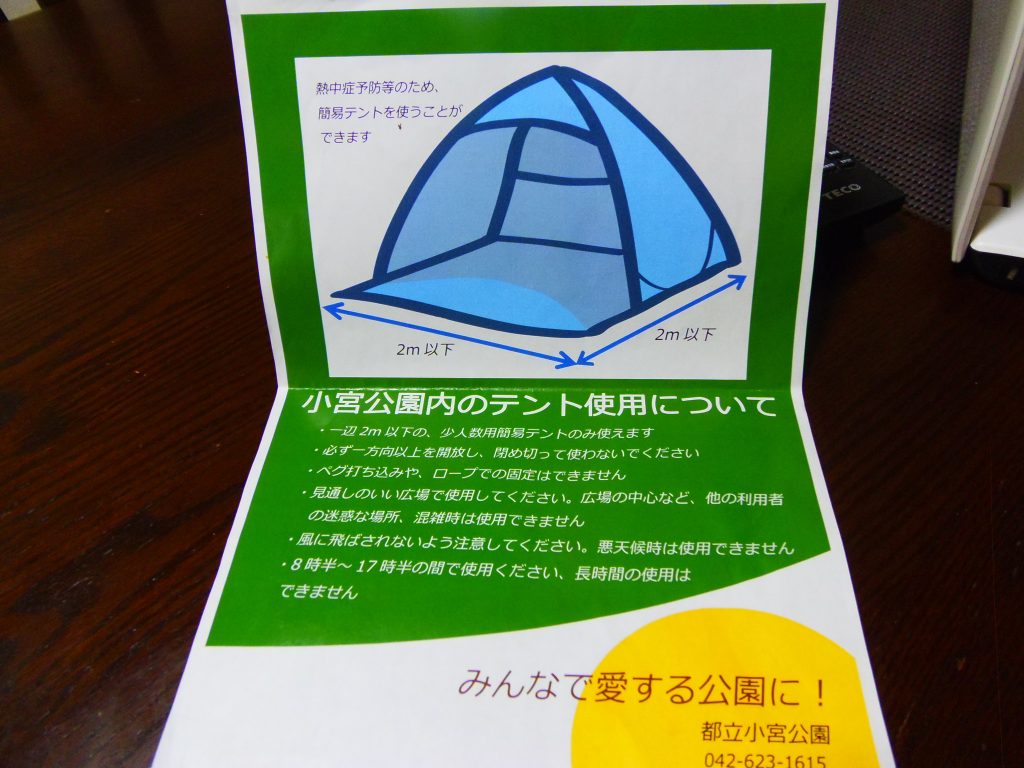【ブログ新規追加838回】

最高のお天気となった、白馬八方尾根登山。
誰が言ったのかな?WEBでは盛んに「白馬でも八方尾根は登山じゃなくて観光だよ」とか、「普通の服と靴で大丈夫」とか。ここは、登山装備(軽登山靴、手袋、ヘッドライト、雨合羽、長袖の服、トレッキングポール、ザック、水、方位計、簡単な食料、帽子、サングラス)が必要な山だ。
初心者向けの山だから・・・そんな話を鵜呑みにして登山にはまさかこないだろうと、高を括っていたら、まさかの「素足にサンダル女子」「ノースリーブワンピ女子」「うっすい靴下にシャワーサンダル男子」とか(驚き!)それが何人もいるんだよ。
あんな薄いサンダルじゃ、リフトの乗り降りでさえ怪我しそう。
もうね。サンダル履きでは、まったく登れない八方尾根の登山道。
上から目線のWEB記事には本当にがっかりする。実際に登ってみて言ってるのだろうけど、急勾配で岩がゴロゴロの道なのよ。
これを一歩、一歩、歩くんだよ。
タイムコースもっと長く取った方が無難。
リフト乗り場で、わたし達は11時に下山し始めた時、登ってきた高齢の男性がやはり高齢の女性軍団を引き連れて、「まだ11時でしょ!大丈夫!時間はたっぷりあるから!」と。
リフトの最終は16時30分。相当急がねばならない。タイムコース通りに行くと往復だいたい3時間弱。
で、11時からでは2時?無理だよ。そんなに早く登れないし下山もできない。とても危険な滑落箇所も多い。(女性はトイレ休憩も長めだということを忘れてはいけない)
初心者向けとか書かれていても、初心者向けでない山がとても多いと感じている。「若くて健脚」でない場合、WEB記事の鵜呑みは絶対にダメだ。
と、冒頭からミスマッチした様子をつらつら書いてしまった。

WEBでブログを公開している身だから、正確さが一番大事だと常々考えている。
盛った話や、無理を承知で危険を冒す登山は絶対にしないし、そういった記事は書かない。
趣味に毛が生えただけのアクティビティだし(笑)
★
八方尾根はピーク(頂上)があるわけでなく延長先に唐松岳(2696m)が控えている。
時間に余裕がある場合は日帰りで唐松岳のピークを目指す猛者もいるが、だいたいは途中で下山するようだ。

もっとすごいのはキャンプ道具を背負い、唐松山荘という山小屋にキャンプを張って翌日登頂を目指す人もいる。女子でも挑戦する人はかなり多い。
しかし、今日はめっちゃいい天気だったが、ガスが濃く雨もかなり降るので安全に登山を楽しむためには慎重にならざるを得ない。
わたし達は夫の心臓疾患があるから、今回も行けるところまででストップしょうと決めていた。(第一ケルンまで)
それでも、朝一番のリフト(8時15分)を2本乗りつぎ、北アルプス・白馬三山を眺められたし、八方尾根の尾根歩きも実現した。それでも尾根は細くてバランスを崩しやすいから要注意。

そして足下に佇むどこまでも続く雲海。綺麗すぎ(笑)

また、今回は岩の道に気を取られてしまって、カメラの撮影モードが変わってしまい、急におかしな写真(連写?パノラマみたいな?)のも撮れてしまった。これにはがっかりだわ。


やっぱり、こういう部分が初心者っぽいよね。
で、下山時に必ず食べようと八方尾根ソフト(バニラ&ブルーベリー・300円)を食べて満足。

さて、次はどこへ?帰りのリフトで話あった。
次は、今回の色々を踏まえて、お互いに同じ場所をとっさに選んでいた(笑)
とにかく、無理のない、少しずつ経験を積む登山やトレッキング・ハイキングを目指す。
明日は早朝から、長野をもう少し楽しんで帰ろう。
では、また。
※ 白馬三山とは→白馬三山(しろうまさんざん)とは、富山県と長野県にまたがる3つの山(白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳)の総称。その周辺の山岳一帯を白馬連峰と呼ばれる。山域は中部山岳国立公園に指定されている。高山植物が豊富で、代表する山として白馬岳が花の百名山及び新・花の百名山に選定されている。(Wikipediaより)