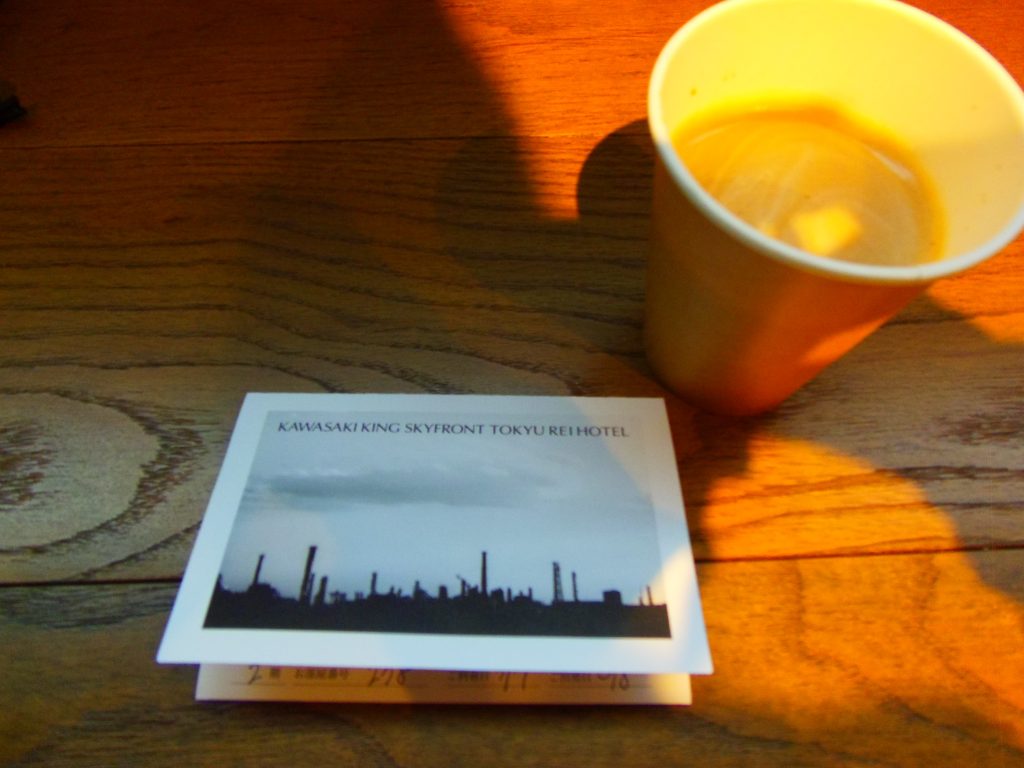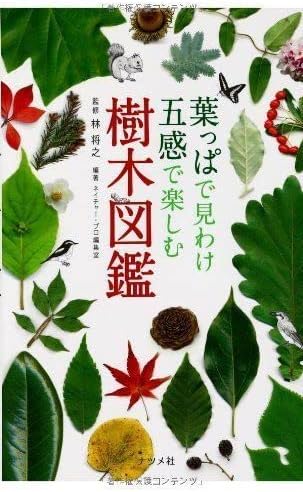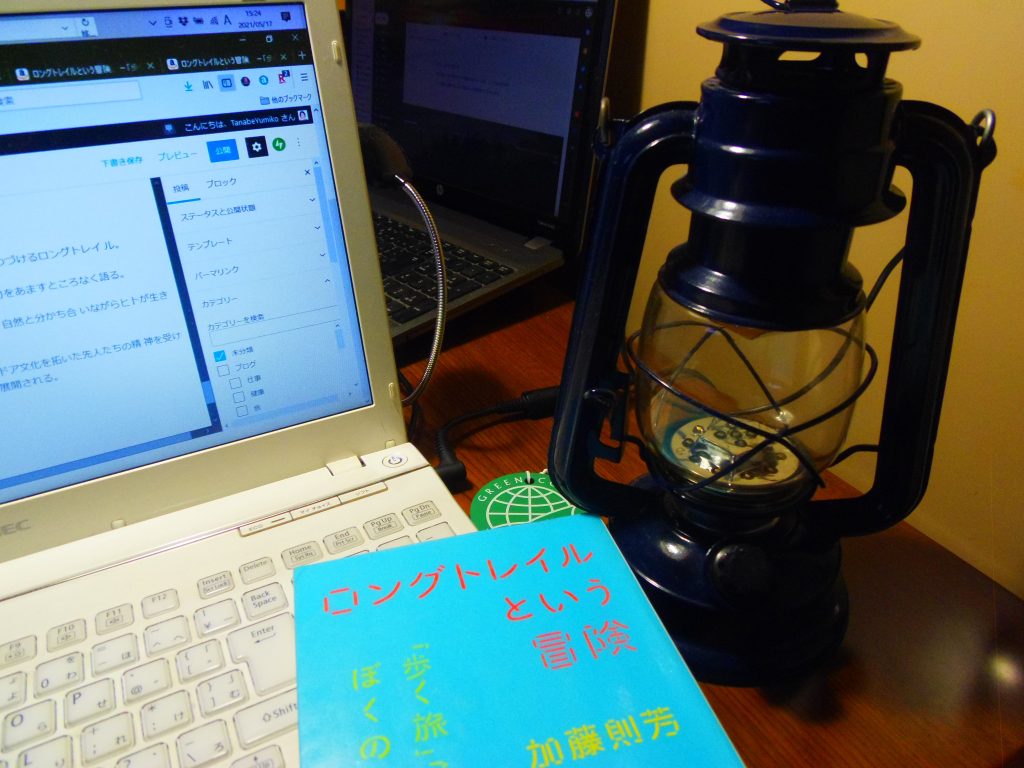【ブログ新規追加393回】

念願だったブルーベリーを樹木から摘み取り好きに食べられる食べ放題をやってきた。
そこは、東京都町田市にある「町田里山ベリー園」というところ。とても山深く、里山の頂上では遠くに富士山を望み、手前に大山が見える見晴らしのよい多摩丘陵の一部に存在している。

2年ほど前に町田市での仕事の折りに、ここを知ってからいつか来ようと思っていたが、コロナもあり月日が流れてしまった。
ブルーベリー摘みのタイミングもあり、どうしても行きたいと思って緊急事態宣言最終日の今日、やっと行ってこれた。
里山の山道は、昨日の雨が残り多少ぬかるんではいるものの、ブルーベリー畑ではまったく足元の不安はなかった。
今の季節では8種類程度の味見ができるとあってウキウキだ。

今日、味見ができるブルーベリーの品種説明をオーナーさんから受けながらブルーベリーの畑に入る。
途中、ヤマモモを見つける。
実がびっしり!これで果実酒作りたい!とか思いながら今日はブルーベリーに注力したいから写真だけにした。たわわになっている実を見ると、つい摘み取りたくなってたまらない(笑)
ヤマモモ、ゆず、びわなど季節折々の果樹が植えられている。たぶんもっと色々あるんだろうが、心はブルーベリーに。

ベリ―の畑では、食べ放題だからと、ほぼすべての樹から熟した紫がかった漆黒の宝石をどんどん食べ続けた。たぶん100個以上!
今月中旬から土日だけ摘み取りができるのだが、まだ実のない若い樹が数十本あった。
それは、これから咲く遅咲きの樹だろう。
しかし、よ~く目を凝らして見てみると、すでに摘み取られた感じがする樹もちらほら。
そういった樹の実はびっくり!するほど甘い。
そして、多く摘み取られている樹の両隣りも同じ品種のような・・・。
だと勝手に思い、そこも摘み取り対象として籠にどんどん入れてゆく。大きい粒は100円玉ぐらいある。
驚き!

実の摘み取られた樹を見つけるのが、大事な摘み取りの術(笑)だったようだ。
それでも、まだ固く酸っぱい実でもやはり生食は美味しい。
身体の中がきれ~~いになるみたいな幻想を抱く、つかの間の食べ放題だった。

そこから、里山のトップオブヒルへと向かう。しかし暑い。里山のアップダウンが激しいから滝のような汗が流れた。
あれ?今日はハイキングじゃなかったっけ?と、自問自答したよ。だってトレッキングだったのだもの(汗)
そこからもうひとつのブルーベリーの畑を眺めつつ、わたしはしばし休憩。夫だけがブルーベリーの畑までトレッキングしてきた。
それにしても、農園内はすごいあじさいの園。これだけのあじさいを鑑賞できる場所は少ないかもしれない。
広大な里山の起伏を上手に利用したあじさいの小径。
オーナーご一家の手入れと管理は並々ならぬものがあるだろう。
あまりにきれいなあじさいを撮ったので数枚選んでみた。




もう、当分海外にも行けないのだろう。
若い頃、イギリスの古い町でB&Bを車で泊まり歩く旅に憧れていた。旅の途中の村でイチゴや数々のベリーを摘むとか、農場で生みたて卵をわけてもらうとか、とにかくオフロード旅がしてみたかったの。
未だ実現してはいない。
それでも、日本には里山という素晴らしい文化がある!と思い出し、「低い山と緑に抱かれながら、地産地消の食べ物や地酒を頂く旅」に方向転換をした。
それに、ピクニック気分だったら籠バッグにワインとパンとお気に入りのチーズと水を持って行くだけで、立派なピクニックとなる。
今日も暑い平野サイトでお弁当を広げる家族がいたっけ。
憧れのブルーベリー摘みも里山も実はとっても身近にあったのだ。

海外熱はとうに冷めて、日本の美しいものに夢中だ。
だってこれほどきれいなあじさいロードや美味しい果樹が近くにあるのだから。
(摘み取り籠を持って、前を歩く夫を撮ってみた)