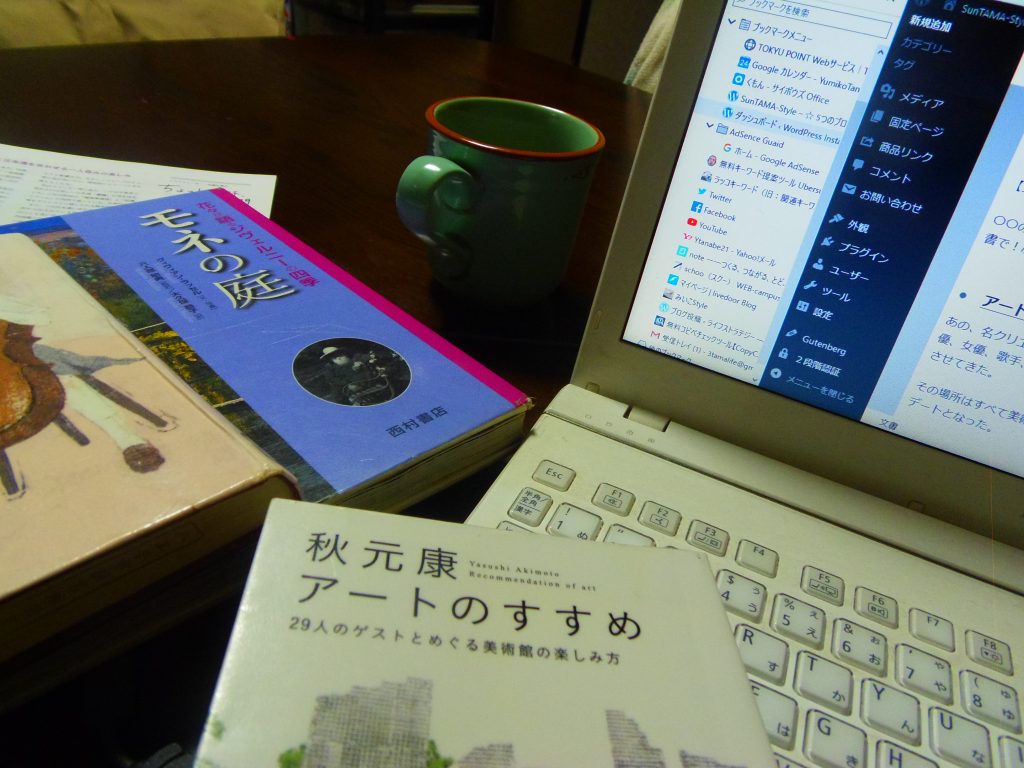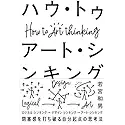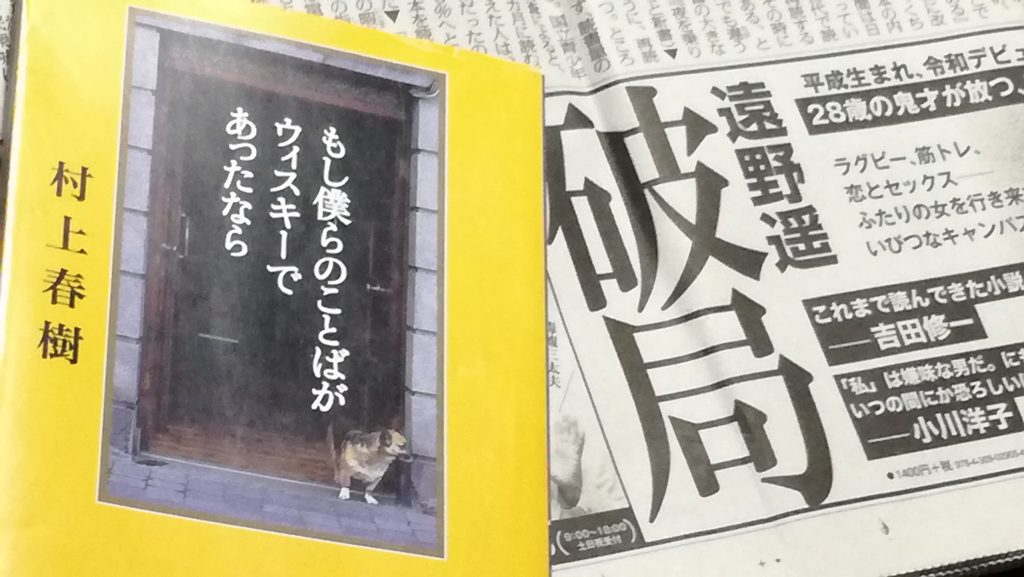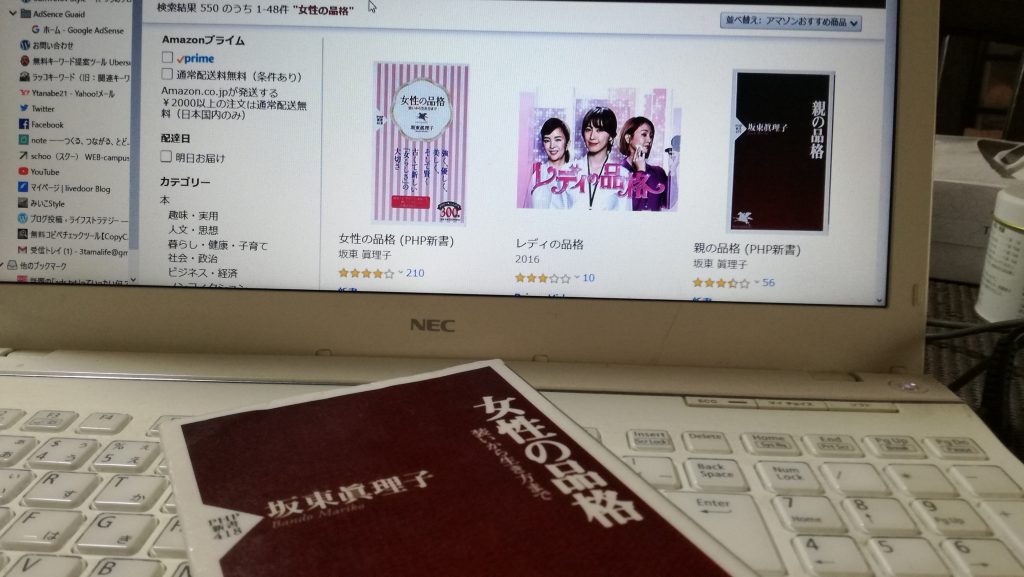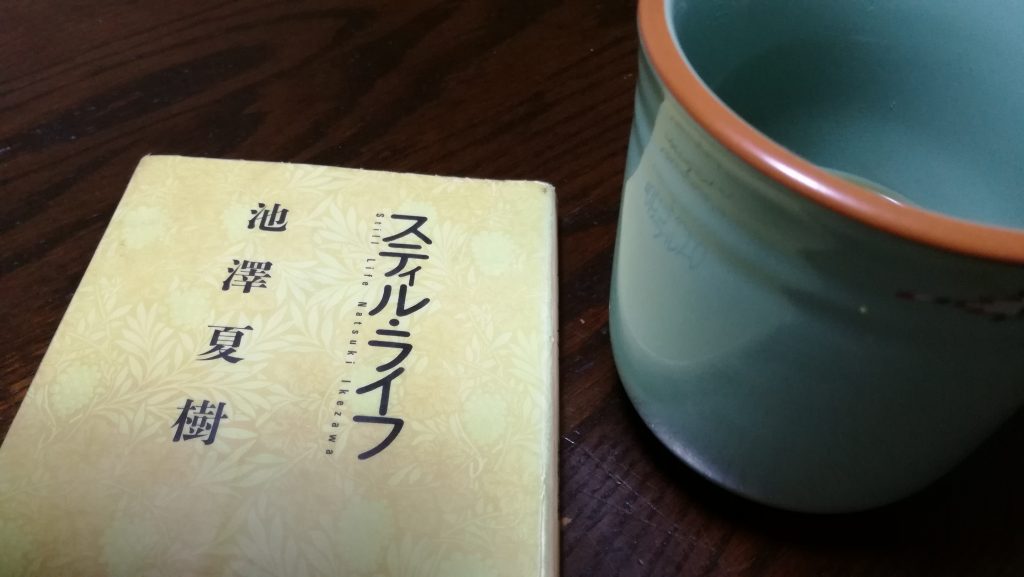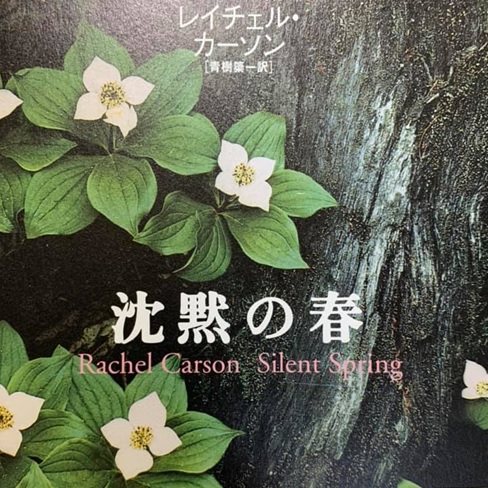【ブログ新規更新181回】

● 「力」というタイトルが流行った背景とは
このブログで取り上げてきた書籍もゆうに100冊は超えているが、「〇〇力」とついた書籍の多いことに気づいてちょっと筆をとってみた。
2012年頃「聞く力」阿川佐和子氏(文春新書)がブームの火付け役になったんでは?と、推測する。
新書ブームが起こったことでも話題になった超ベストセラー。
実際にはご本人のインタビュアーとしての立ち位置に関する事柄が大半で、アイスブレークの仕方や人の本音、以外な言葉を引き出したエピソードが満載だったように記憶している。
さて、ここでは、「〇〇力」とタイトルに「力」を入れた書籍の紹介をする。読んだ本だけ。
などまだまだあげれば切りがない!新書の ” 力ブーム ” が続いていた。
もう、本当に誰もが「力」とつく本を書いている。
まるでトレンドキーワード、言葉の力に大きく左右されているなと大いに感じた現象だった。
● キーワードの持つ影響力とは
影響力・・・「他に働きかけ、動き、考えを変えて行く」
確かに「聞く力」のように何週間もベストセラーのトップにランクインしていた本は、手に取った人の多さでは影響力を持って世間の新書を求める動向を変えたと思う。
しかし読んだ人が皆、動きや考えを変えたか??という点では分かり得ない。
また「力」に変わるキーワードが出てきたら、皆一斉に有名、無名に関わらず、キーワードに飛びついて執筆、出版されてきたのは明らかだ。
私としては個人の時代になって誰でも自分の記事、作品をアピールできる昨今では「話題の先取り」これに尽きるのではないか、と感じている。
テレビ、新聞などのメディア離れが叫ばれているが、どうしてまだまだメディアの持つ情報量の膨大さや、物事の真意など世間の圧倒的な支持を得ている現実がある。
そこで個人も横並びに勝負できるとすると、「先取り感」「旬」といったキーワードが一番世間が欲しているんでは?と常に考える。
要するに「誰よりも先に!」が必須で、競合していないかなどのマーケティングがしっかりとなされなければ、もう、個人の記事や無名の作家の作品は読まれない。
● 個人の時代の影響力はネット検索すればわかる
「情報」という点で、日常的に私も検索をたくさんかけて情報を集めている1人だが、検索ほど個性がでるアイテムもそうないな、とこの頃感じていた。
例えば今回の「力」に関する情報を集めようとした時に何を中心に集めるのか?これって人によってすべて対照があるので100人いたら100とうりの検索方法がある!ということだ。
ちなみに私がどういう検索をかけていたかというと「〇〇力 キーワード 影響力」という言葉を切ってやってみた。実際は「影響力」のみにスポットが当たってそれに関する事柄がば〜っと羅列されて出てきた。
まあ、当然だろと思うが、捉えにくい言葉などは思いっきり省かれて出てくる。
それだけでは情報が足りない場合は辞典や過去の関連書籍をあたることとなる。
固有の場所などの検索は比較的簡単だが、キーワードを関連づけて検索をする場合のやり方は人それぞれ。
実はこのことは密かに面白いと感じていて、小説のネタやアイテムになるな、と思っている。
● まとめ
今週後半は秋旅をする予定で、真新しい情報を集めている。
今では、紙のガイドブックは買わないし、だいたい持ち歩かない。だから、自分の頭に検索した最新情報を詰め込んで、あとはスマホ検索になる。
現場で出会う検索には反映されてはいない真新しい出会いはブログに書く。こういった生の情報は自分の目利きで調べていくしかないのであろう。
わたしは、現場に出て困る!分からないからやみくもに歩き回る!こうした行動がとても多い。
日頃から、正しく調べることに関して「なめてかかっている」のでそのぶん痛手が大きいのだ(泣笑)
自分の持っている情報が必要に応じて「更新」されているか、またそのことに気づけるかが重要だ。
それには普段から知性の土台を築いて(例えば文章やふるまいなどを磨く)、想像力を鍛えていくことが「情報の目利き」に通じていくことではないかと感じている。
流行ってるからって、何でもすぐ飛びつくのはカッコ悪いよね。
でも、真性の先取りだったら、一はやく伝えて行けば、影響力も倍増するだろう。
それが、メディアではなく、個人発信だったら。誰にでもチャンスは足元に転がっている。
※ 最後に斎藤孝氏の「大人の精神力」からの抜粋をひも解く。
「精神」というと、「鋼のごとく鍛えられた揺るぎないもの」をイメージしますが、環境が激変する現代ではむしろ「どんな変化にも対応できる柔軟な精神力」が必要です。
45歳〜60歳までに上手に精神を保つ環境を整える=ギアチェンジをすれば60歳から先が大きく変わる! 斎藤孝