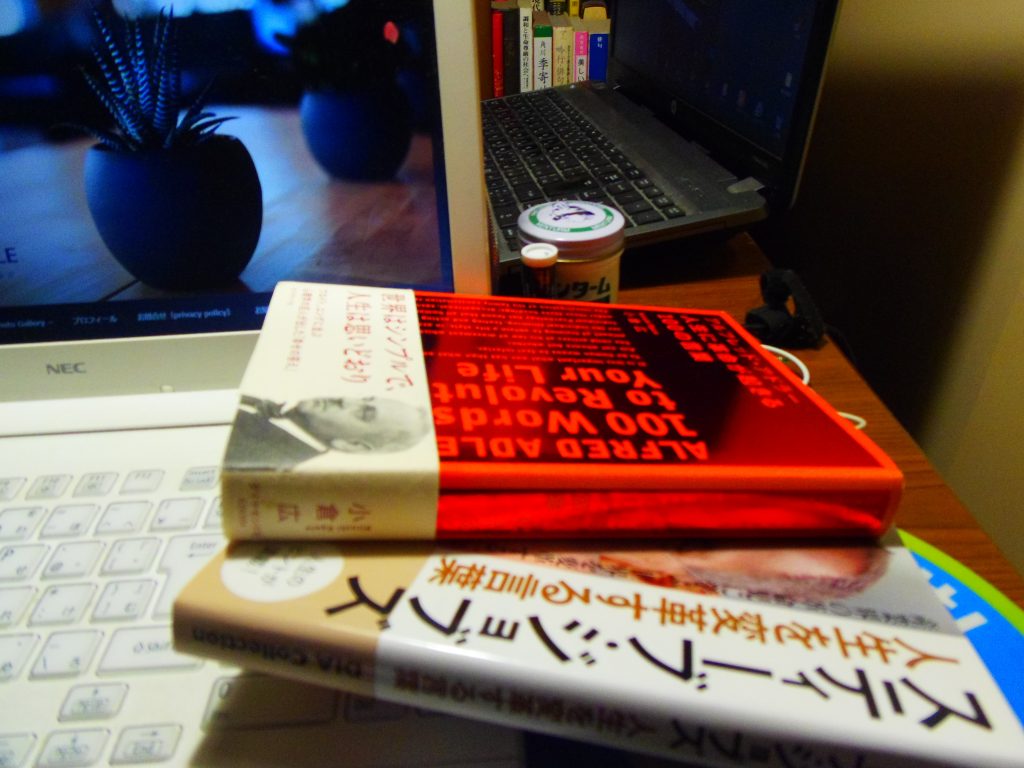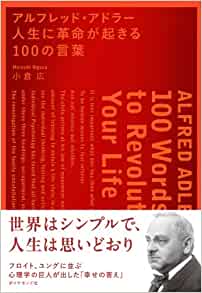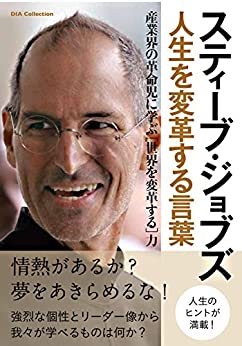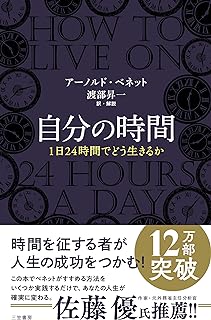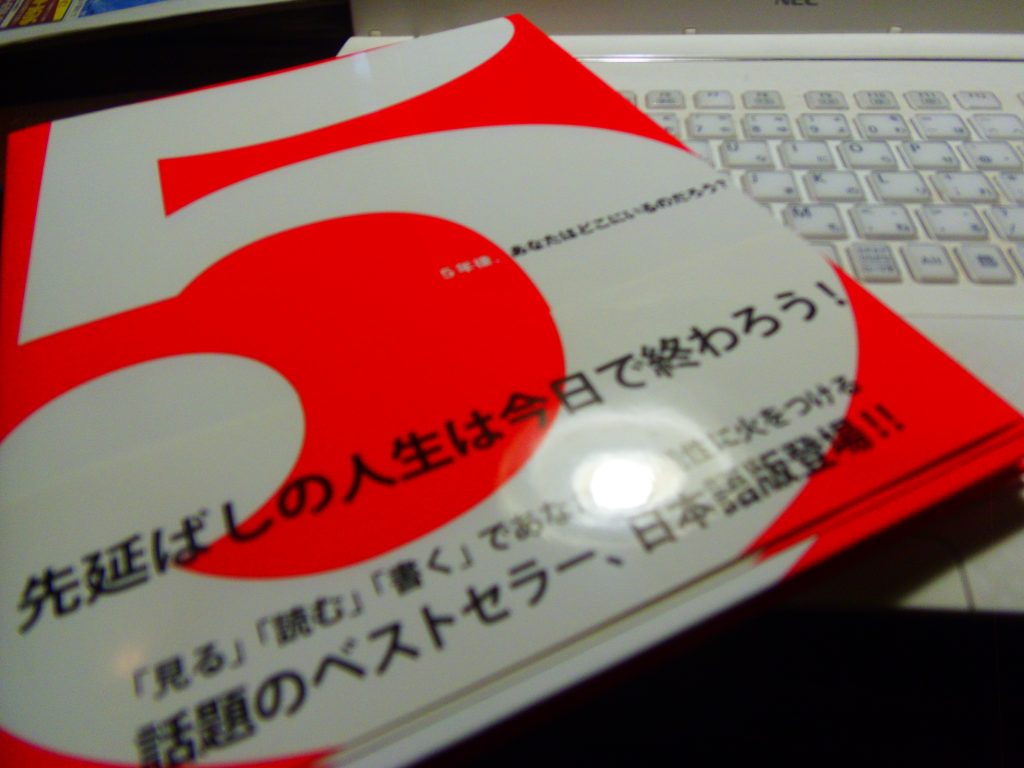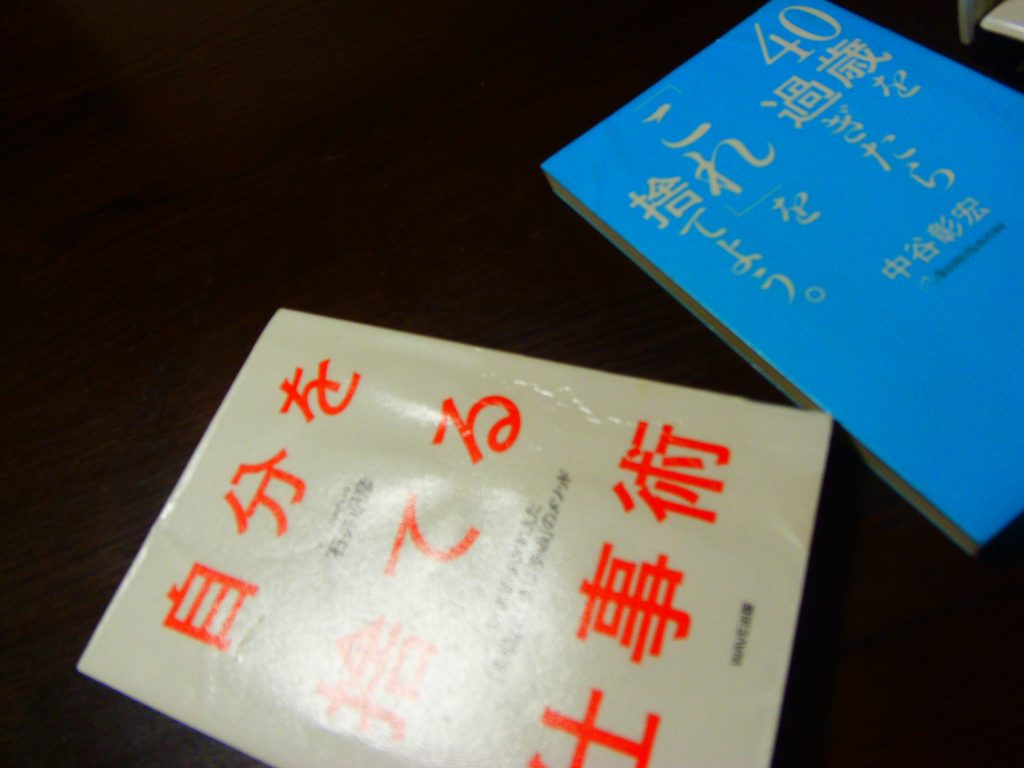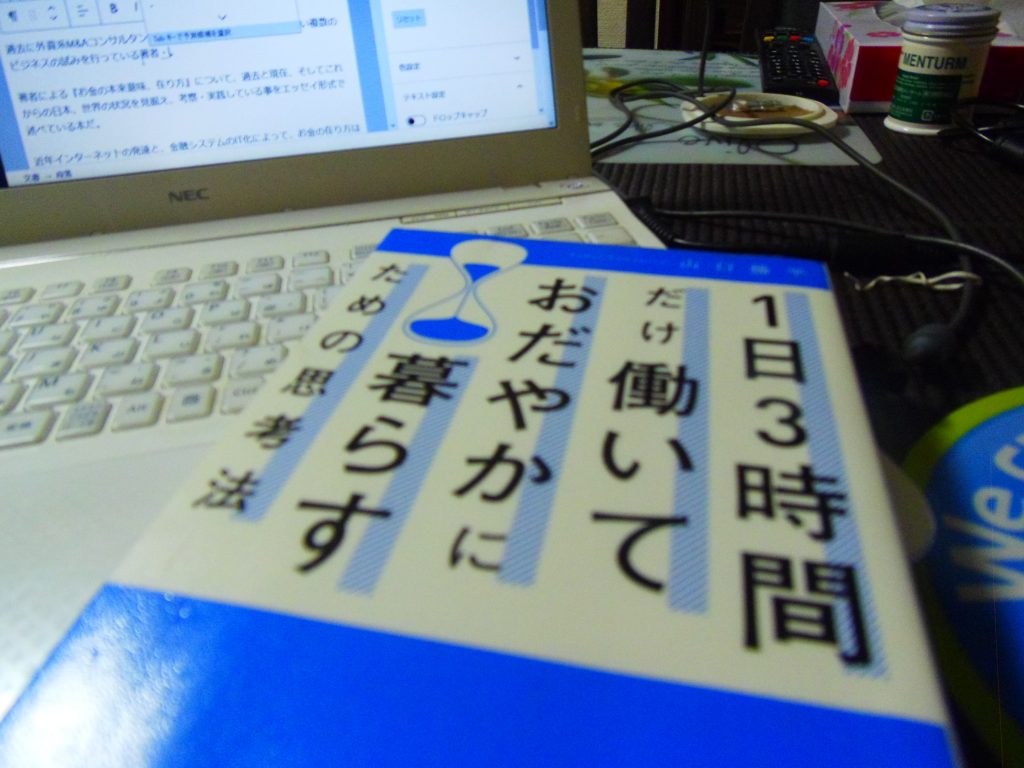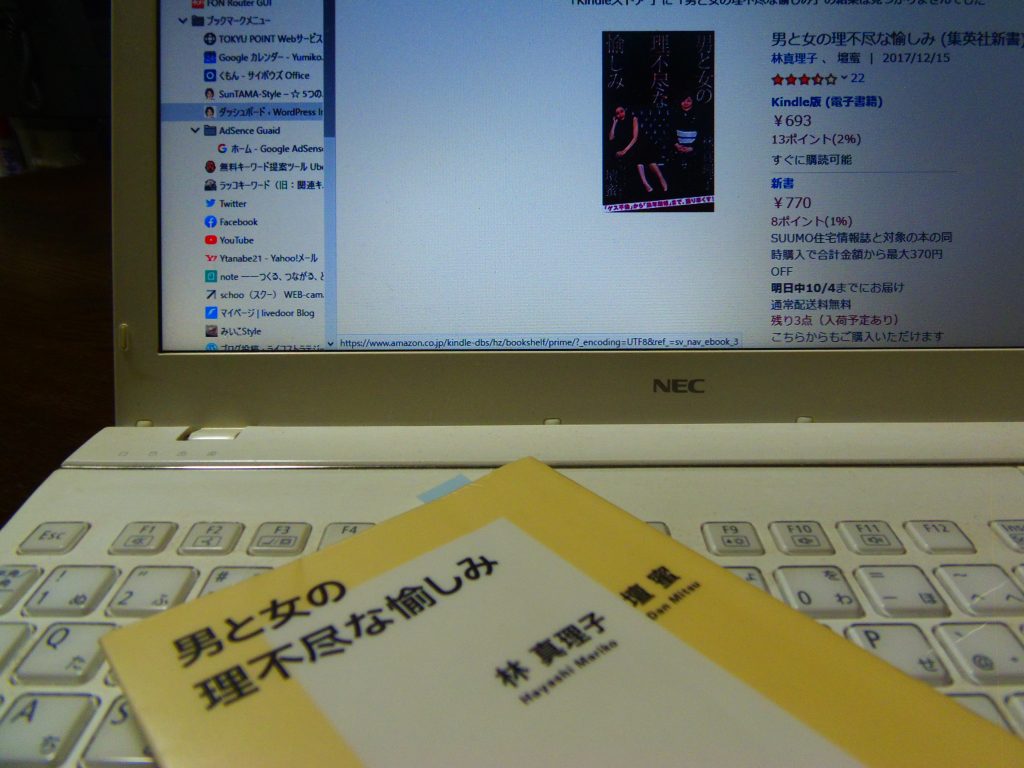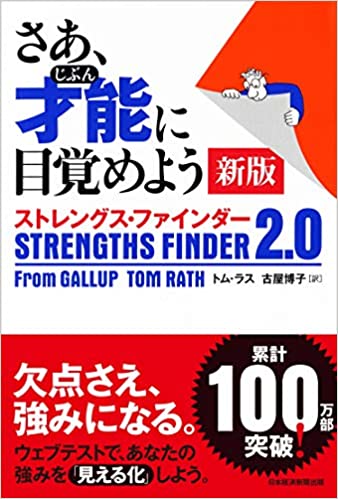【ブログ新規追加332回】

新年度の今月、書店フェアの多くが高齢者作家の祭典。数々ある文藝書籍の中、ひと際目立つのが「高齢女性」の方々の新刊や既刊本だ。
今回は3人ほど紹介しよう。
はじめに昭和を代表する女性小説家と謳われる、平岩弓枝氏(90歳)は満を持しての初エッセイを上梓。
タイトルもすばらしい。『嘘かまことか』(文藝春秋)
● 簡単レビュー
神様の書かれたシナリオを、大根役者の私が必死になって演じてきた……。「御宿かわせみ」の作者による、もうすぐ九十歳の幸福論!
★
次は、人生の「酸いも甘いも嚙み分ける」痛快な文章を連発してきた佐藤愛子氏(97歳)
こちらのタイトルも同じく素晴らしい。『何がおかしい!』(中央公論社)
● 簡単レビュー
2020年秋、九十七歳。
あの超面白スーパーエッセイが帰ってきた!
女と男、虚栄心、知性と笑い、子育て、教育……、世間の常識、風潮に物申す。
今、読んでも新しい愛子節が全開。
『気がつけば、終着駅』と併せて読みたい、必携の一冊。
文字が大きく読みやすい、新装版で登場!
と、内容通りのササっとしたレビューを書いてみた。
★
3人目は、作家さんではなく、料理研究家の村上祥子氏(78歳)先のお二人よりまだまだ全然若い(笑)
御年78歳現在の、快適仕事術を余すことなく披露したビジネス本。
ハードな料理研究家という仕事を楽しみ切る村上氏。読むだけで元気になる美味しく、おしゃれな本だ。
『78さいのひとり暮らし~ちゃんと食べる!すきなことをする!』(集英社ビジネス本)
● 素敵な本だったので徹底レビュー
「ちゃんと食べて、ちゃんと生きる」。村上さんの実践する「食べ力」 は、生き方の栄養学です。野崎洋光さん(分とく山 総調理長)・・・帯より。
これまでに出版した著書は500冊以上!
生き方、家族、仕事、暮らしの知恵から
80代の夢と計画、おすすめレシピまで。
78歳の料理家・村上祥子の元気の秘密がまるごとこの1冊に!
【各章レビュー】
社宅に住む主婦だったときに、料理コンテストで優勝。
その後、料理研究家として活躍を続け、地元・福岡と東京を頻繁に往復してきた村上祥子氏。
管理栄養士として、糖尿病、生活習慣予防改善のためのカロリー控えめで栄養バランスの優れた食事を考案し続け「たまねぎ氷」「にんたまジャム」など健康に良いアイデアレシピを創ってきた。
「ちゃんと食べて、ちゃんと生きる」
現在までぶれない考えが生まれたのは、30代後半で顎骨の骨髄炎を患ったときだった。
40代に入って病名が判明し、10回の手術で抜歯18本。闘病生活は4年に渡ったのだ。
「華やかなごちそうよりも、おしゃれなメニューよりも、堅実な食生活が大切」と。
憑き物が落ちたように、食べる意味を悟りました。
現在78歳。
子どもたちは独立し夫は6年前に先立ち、後期高齢者のひとり暮らし。
1日3食ちゃんと食べているけれど、手間は省いて簡単に。材料をマグカップに入れ電子レンジでチン! の「マグカップごはん」など。
肉、魚、野菜をフリーザーバックに入れる「1人分冷凍パック」も必須だ。
料理教室で生徒のニーズを知って編み出したメニューを私生活でも実践してきた。
よって、体調は絶好調である。子どもたちの食育と、自立するシニアのための料理教室に力を注いでいる。
80代の夢は、美味しいランチを提供する「村上食堂」のオープン。
世界のおばあちゃんを取材して、とっておきのお菓子の作り方を本にまとめること。
好きなことを続けるために、ちゃんと食べ続けているのだ。
人生を振り返りながら、気負わない毎日の暮らしぶりを紹介、実際に食べているごはんのレシピをお届けする。
●著者について
村上祥子(むらかみさちこ) 料理研究家、管理栄養士、福岡女子大学客員教授。
1985年より福岡女子大学で栄養指導講座を15年担当。
治療食の開発で、油控えめでも1人分でも短時間でおいしく調理できる電子レンジに着目。
以来、研鑽を重ね、電子レンジ調理の第一人者になる。
★
さて、3人の後期高齢者の皆様の珠玉の一冊を紹介させて頂いた。
読むだけで元気が出る書籍の数々。
嘘だと思うなら、ぜひお試しあれ!
彼女たちのパワーの虜になるハズ(笑)
● おまけ
エベレスト女性初登頂登山家・田部井淳子氏の名言が生んだ一書。
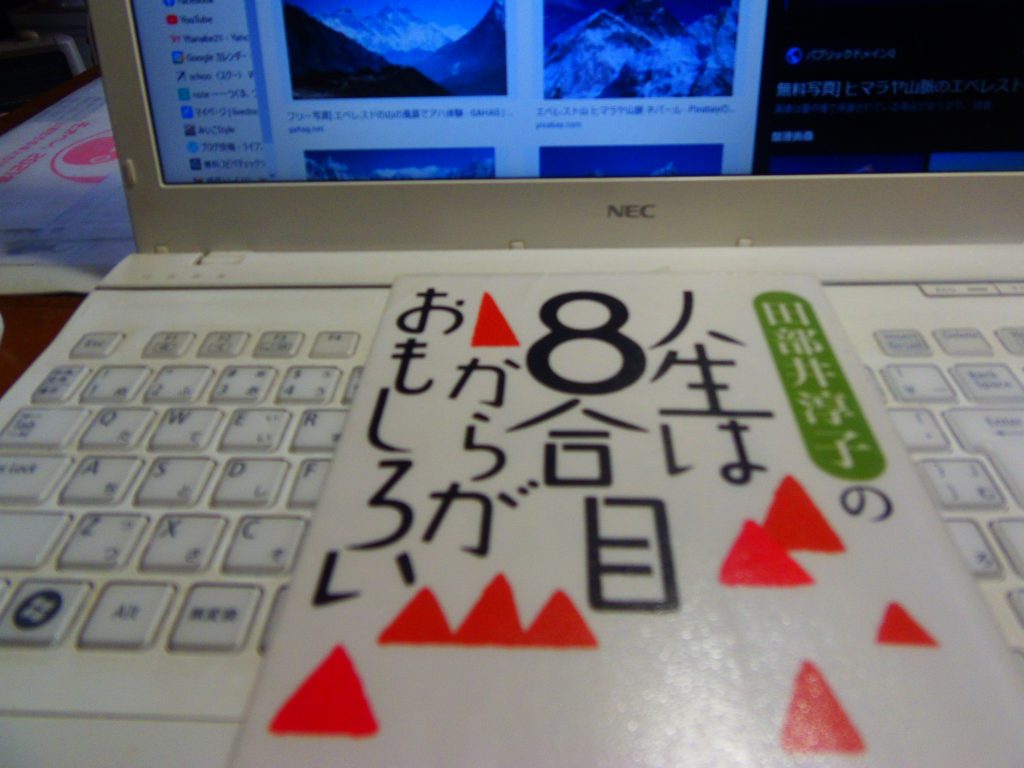
「人生は8合目からがおもしろい」(主婦の友社)
田部井氏が60歳の時に書いた銘書。常にチャレンジをし続けてきた登山家。60歳になってやりたいことが爆発!それを見事にやりきって逝去。
こちらもタイトルが素晴らしい!
● 簡単レビュー
59歳までに登った海外の山……約85
60歳以降に登った海外の山……約85
女性としてエベレストに初登頂を果たした登山家・田部井淳子氏。
70歳を超えるも、年に数回の海外登山や、NHK を中心としたテレビ出演、講演会、健康山歩き教室の開催など、元気に活躍されてきた。
本書は、これまでの「登山ガイド」とは異なり、60歳からの「ドキドキわくわく」な人生について語ったエッセイ集だ。
大切な友人や家族の話。
60歳を過ぎてからチャレンジしたアレコレ、海外登山のエピソードなど、田部井淳子氏のギュッと濃縮された日々が綴られている。
この春はお姉さまがたの本で人生勉強中!
わたしなどは、まだまだ「ハナタレ小僧」だもんで(笑)