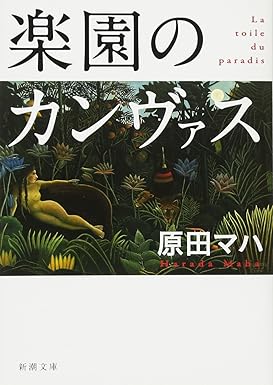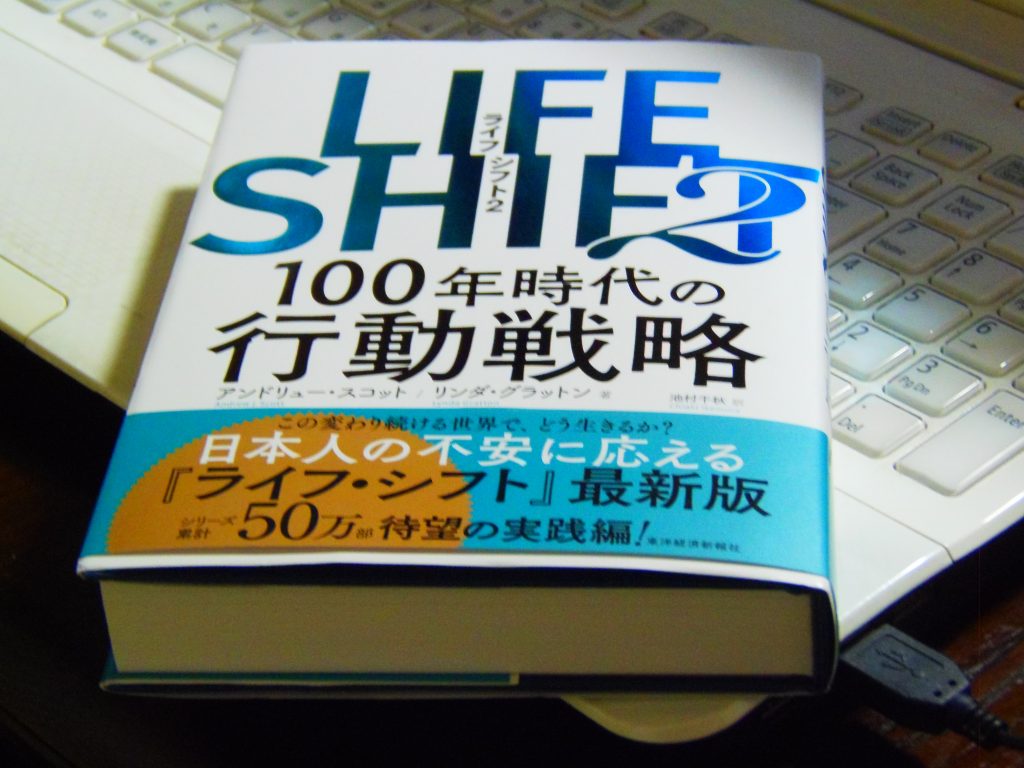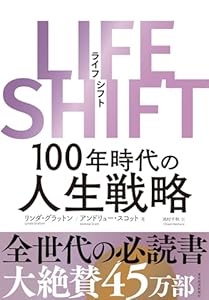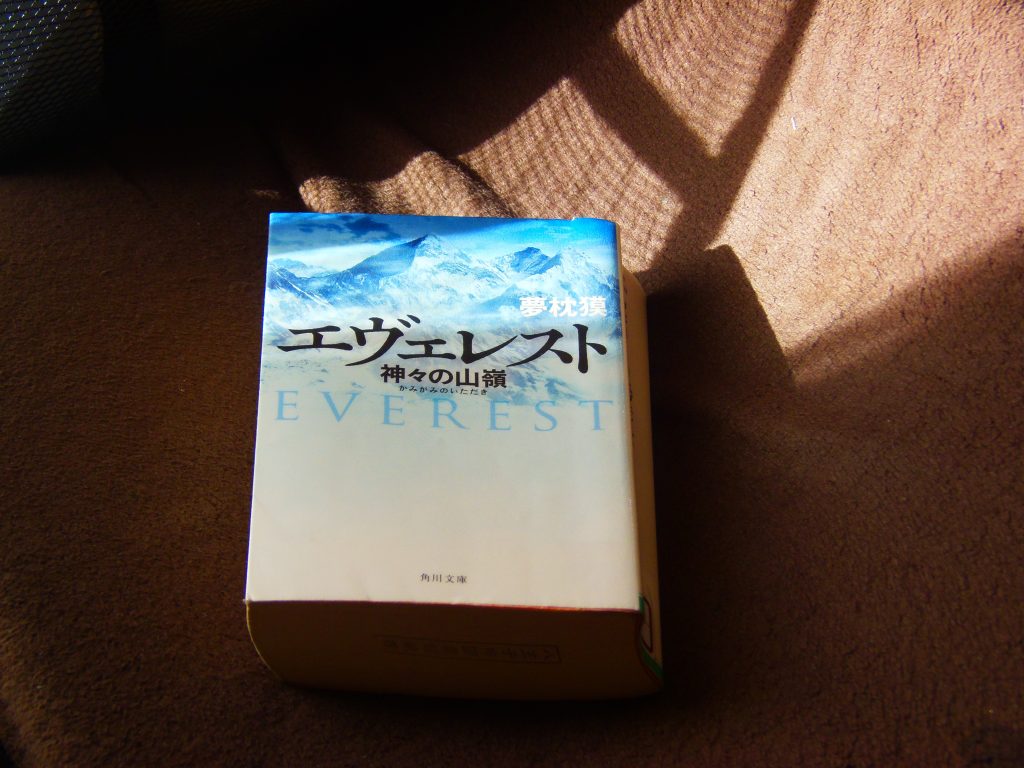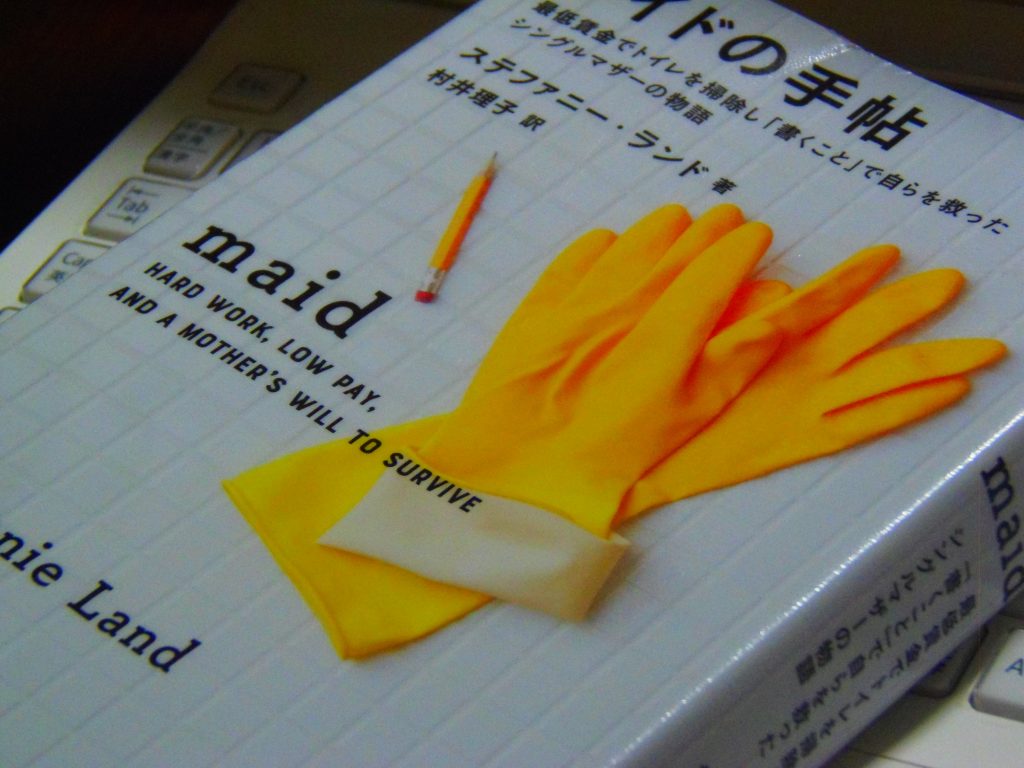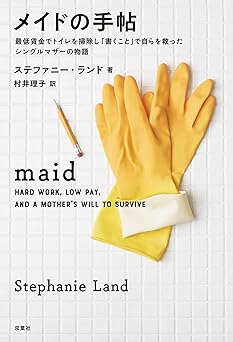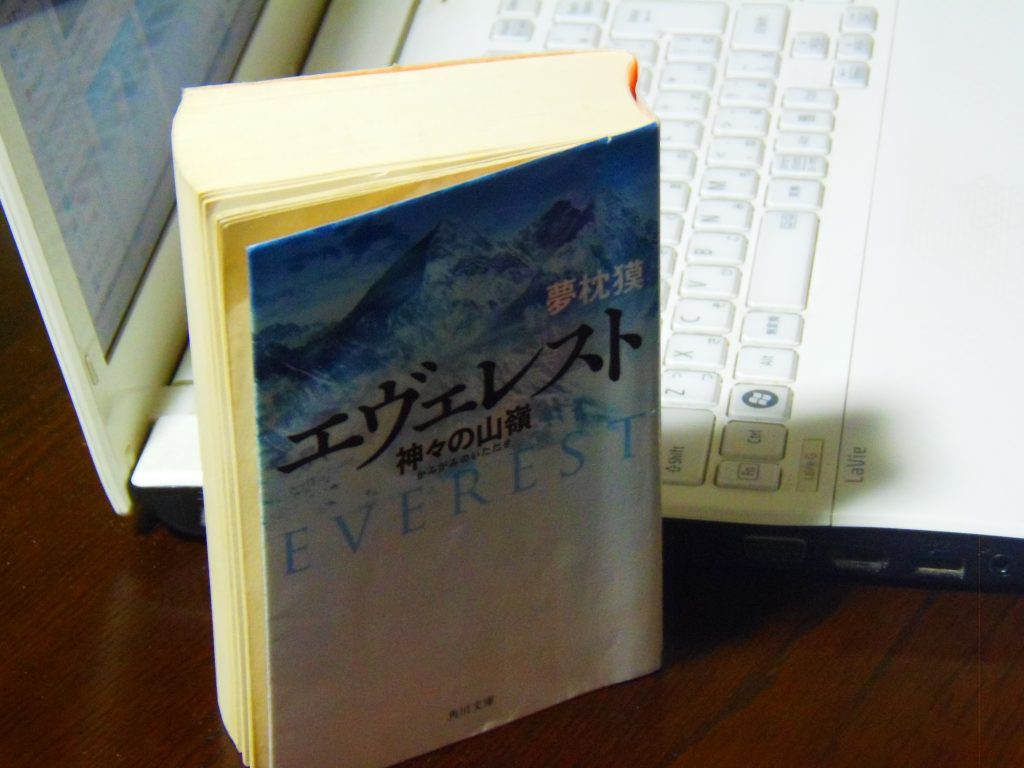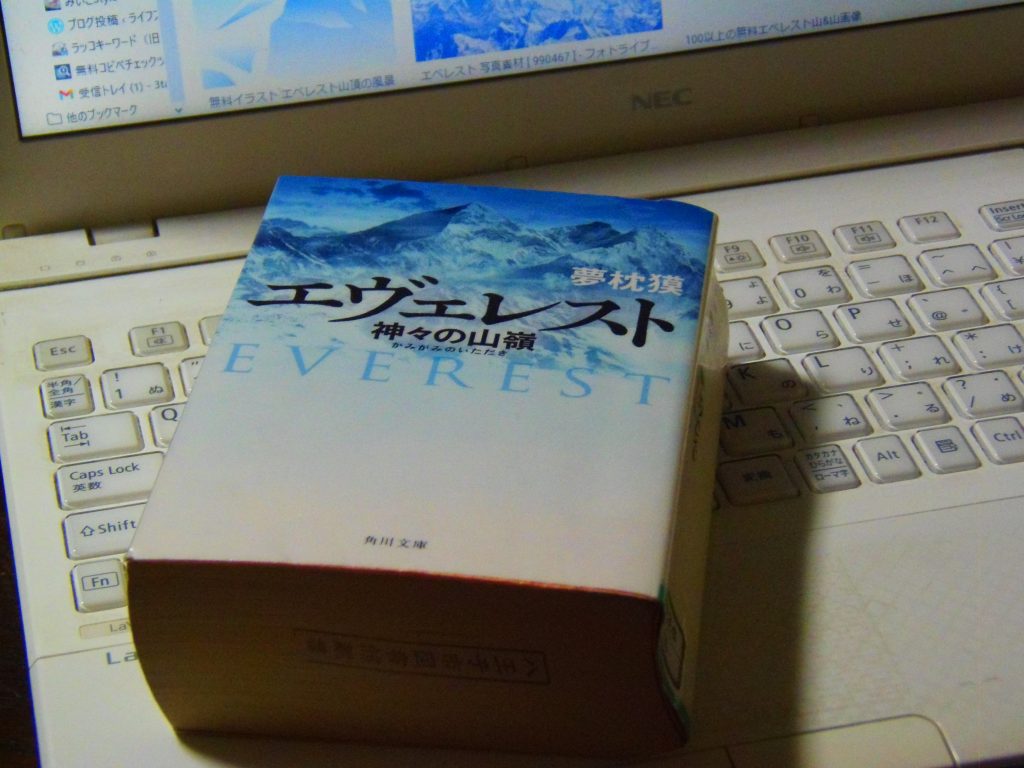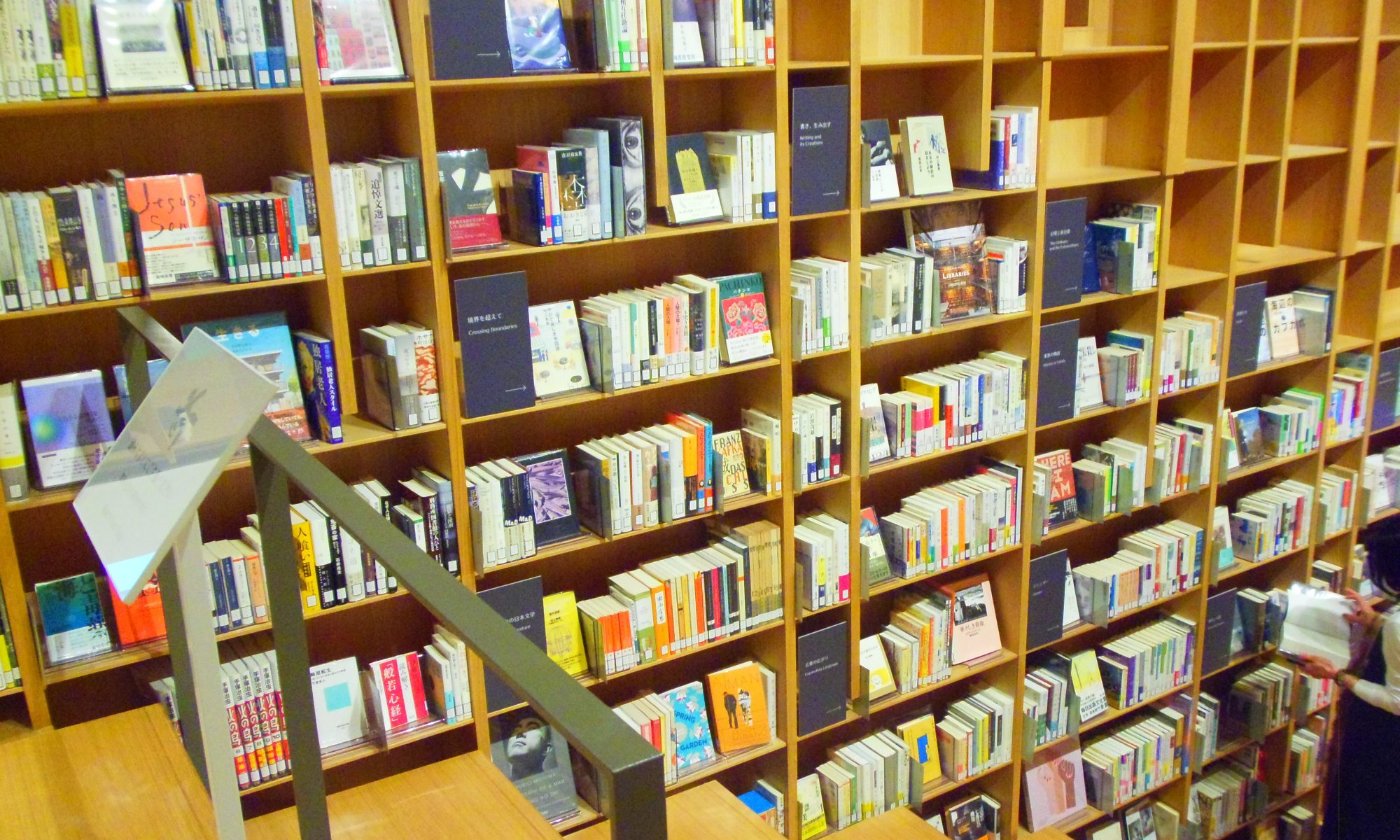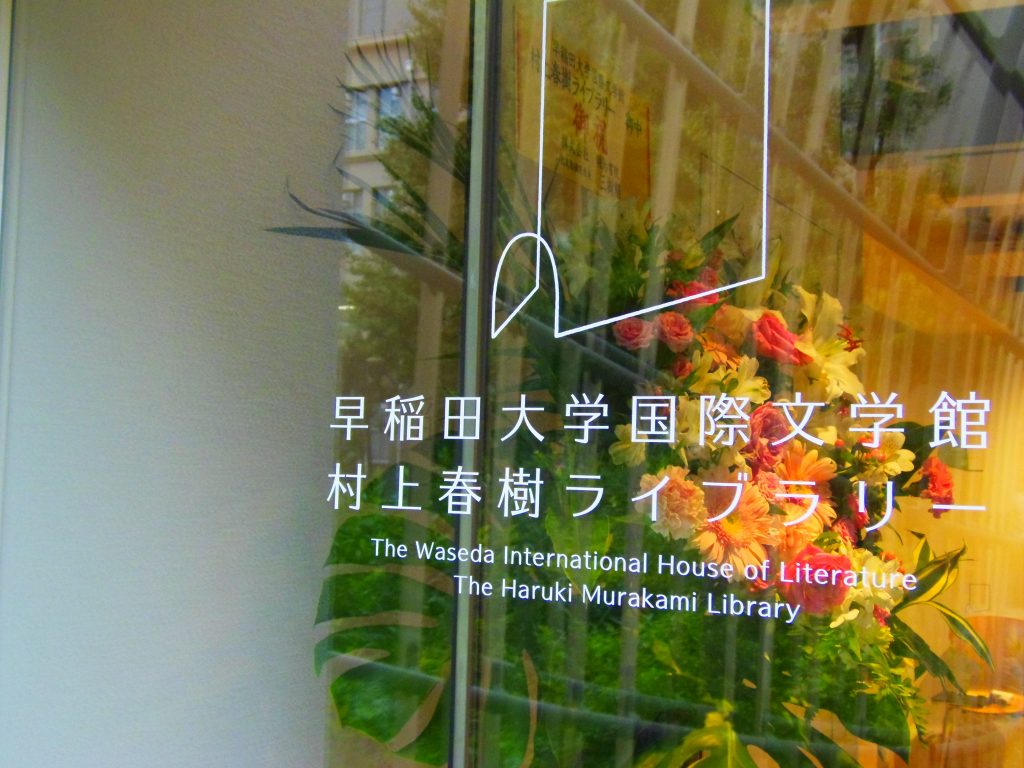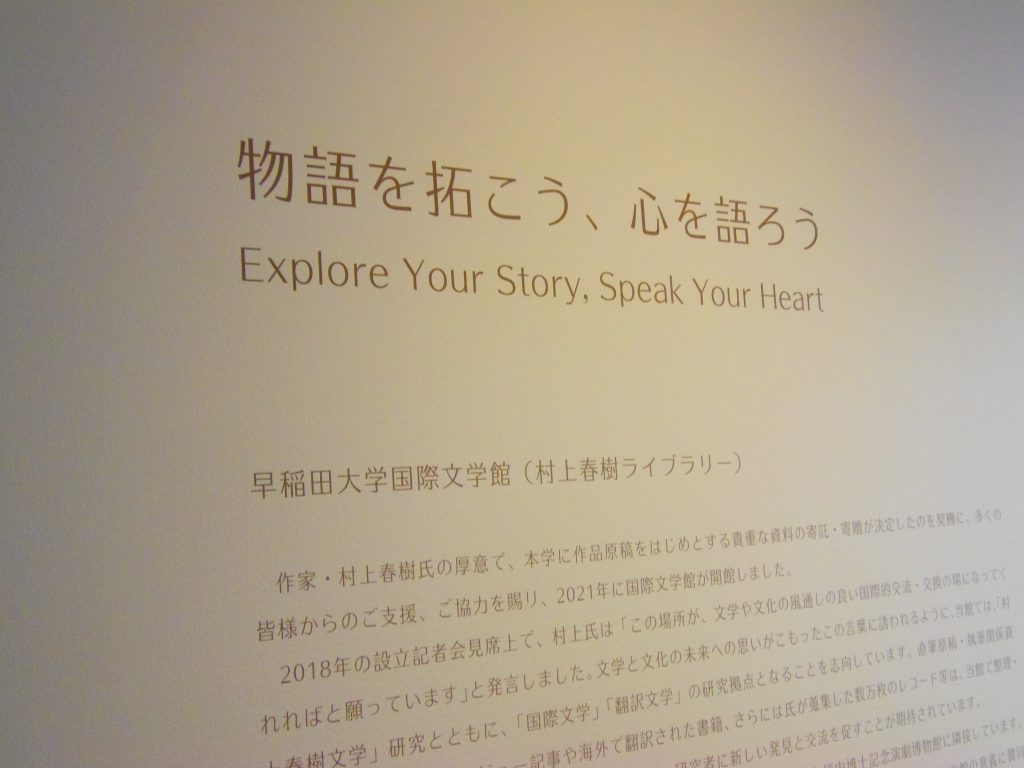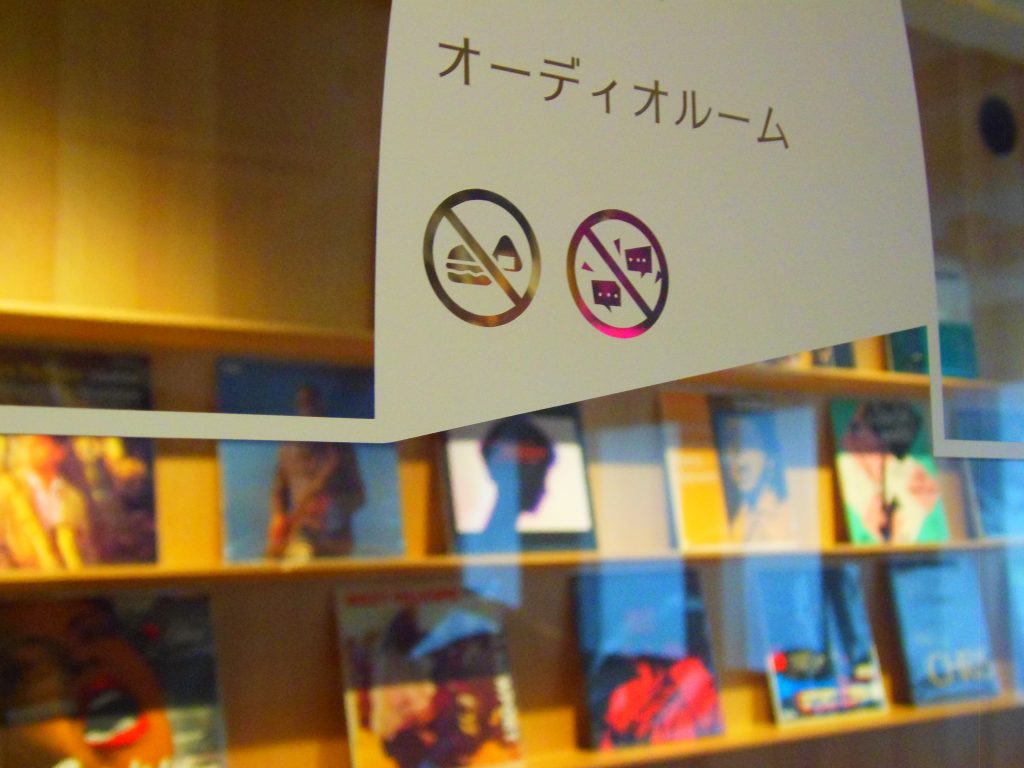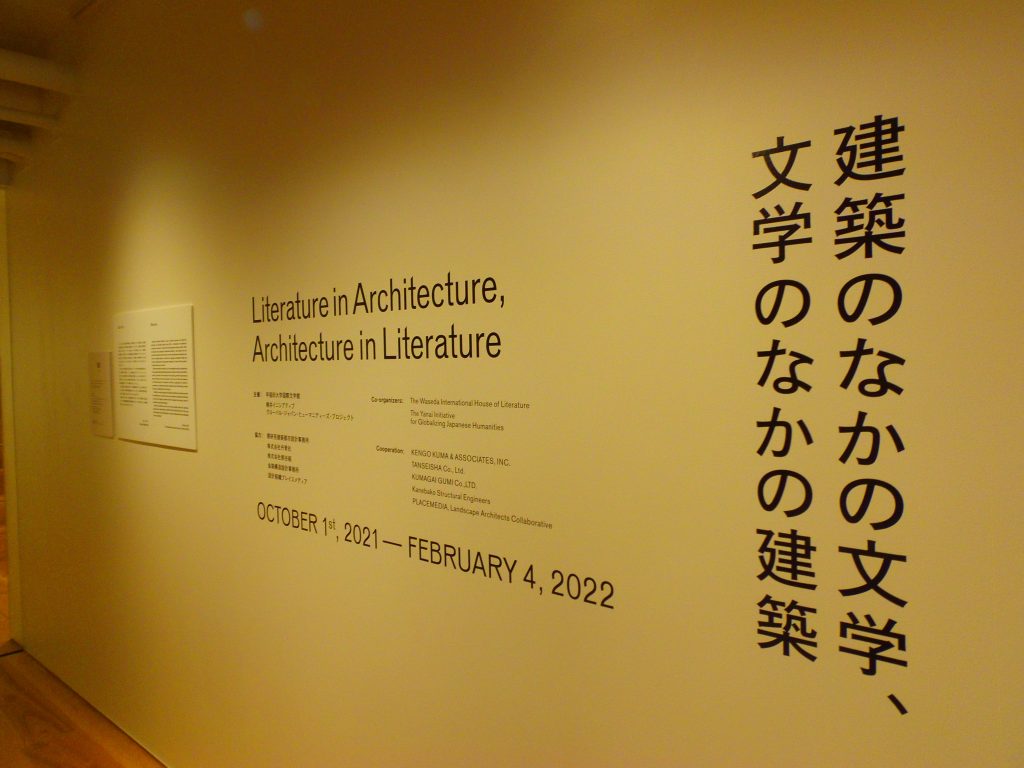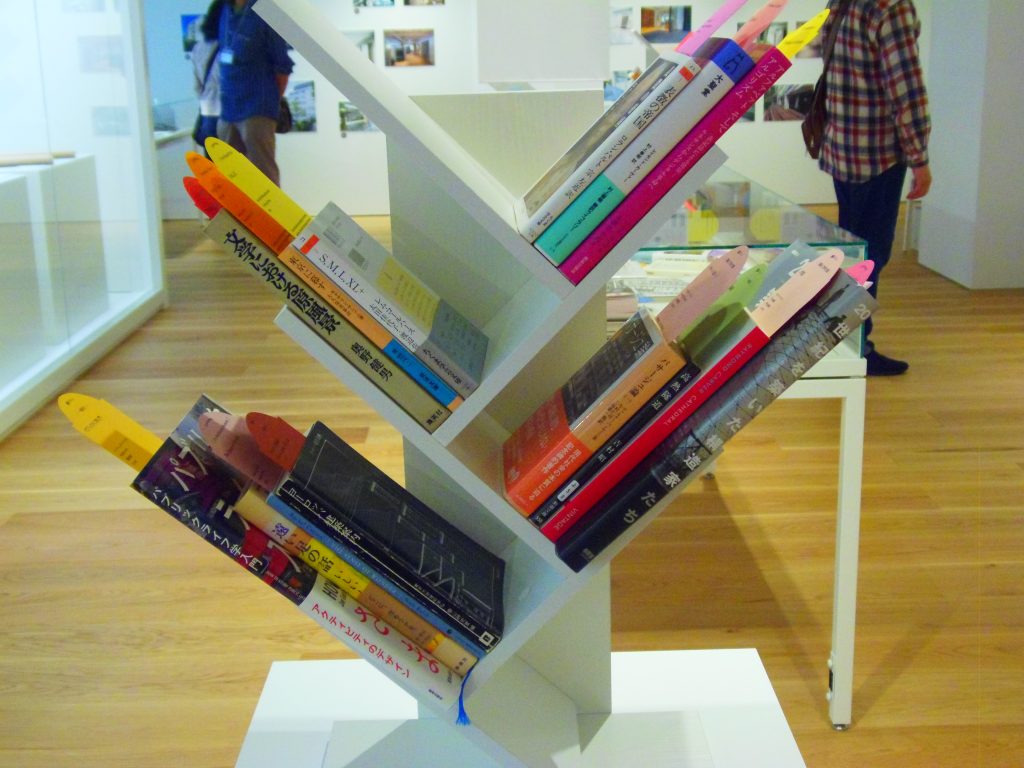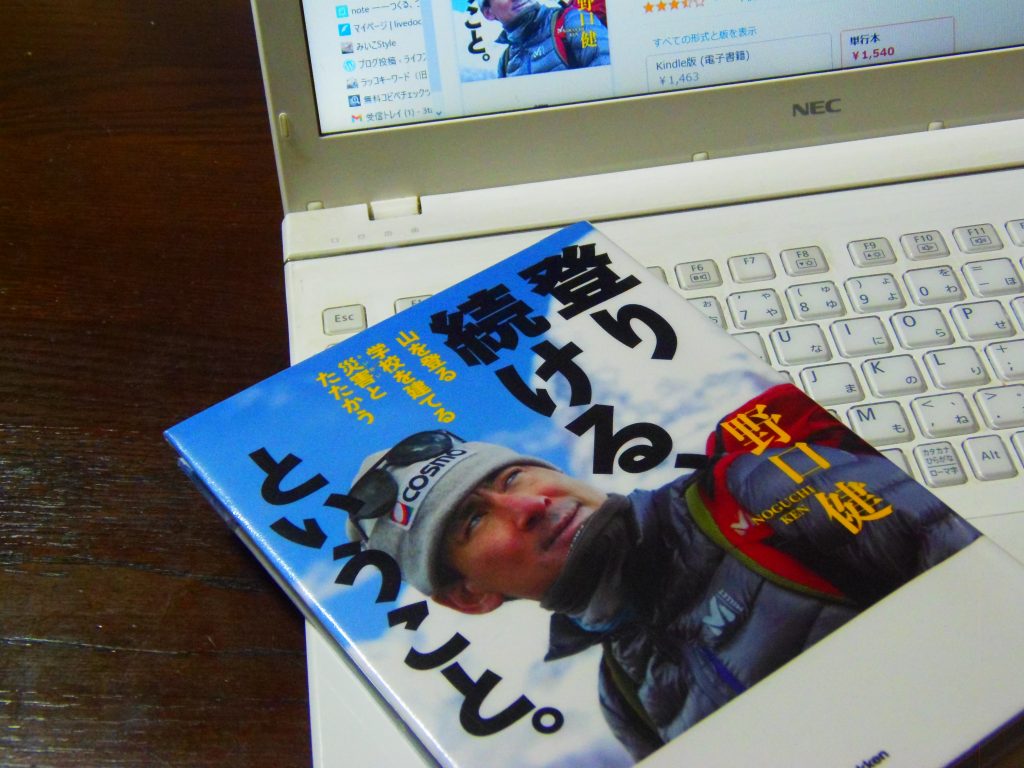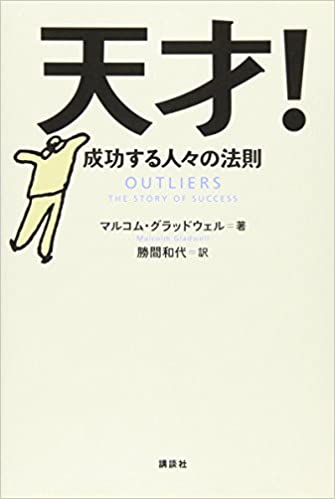【ブログ新規追加554回】
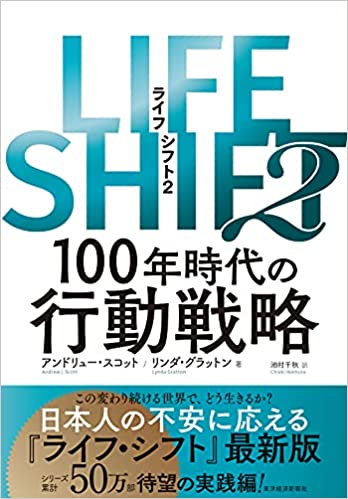
11月、かなり多忙だったが、懸案だった『LIFE SIFT 2』~100年時代の行動戦略~を読み終えて何だかホッとしている。
わかりやすくレビューするために、『LIFE SHIFT』『LIFE SHIFT 2』と一挙に2冊の紹介をする。
世界的大ヒットした前作『LIFE SHIFT』~100年時代の人生戦略~では、読み終えて背筋がピーンと伸びたものだった。
誰もが、人生100年時代を生きる。誰もが主役となれるポイントが挙げられていたのだ。ここにそのポイントを本文から抜き出してみよう。
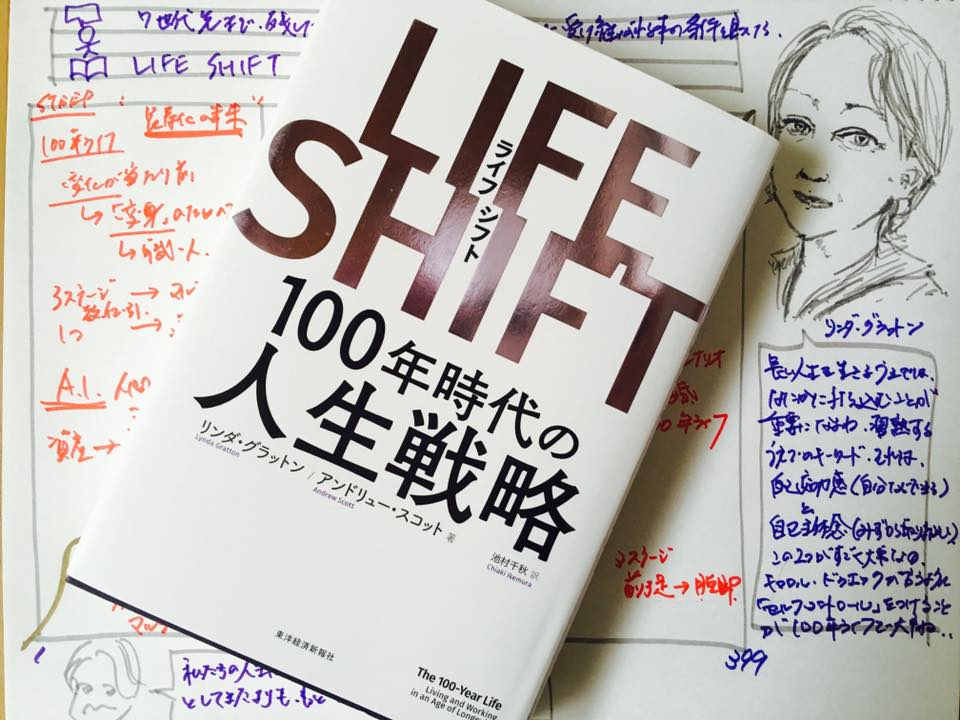
「ライフ・シフト」~100年時代 の人生戦略~最重要のポイントを挙げてみる。
未来を予測するに、これから先はこんなことが起きます!
◉ 50歳未満の日本人は100年ライフを過ごすことになります。
◉ 定年で仕事を終えて余暇を過ごす人生ではなくなります。
◉ お金より、目に見えないもの(友達、健康)などが大切になります。
◉ 男性一人で家族を養うモデルは崩壊します、
◉ 夫婦の信頼関係がより重要になります。
まとめるとこんなところだ。私たちが元々もっていた人生の価値基準は3ステージ型で、おもに学習~仕事~余暇で、大事な物は家やお金などの有形財産というものではなかっただろうか?
これに対し、自己変革するという方向が、これから先に通じていける唯一の道というか希望というのか、リンダ女史の唱える100年ライフの価値基準となる。すなわち、学習・仕事・余暇が途切れることなく生涯続き、大切なのは物より無形財産寄りのスキル・健康・友人・仲間・評判などにシフトすることで、人生の希望が叶えられていくというもの。
今まさに私も、自己のスキルや健康・仲間・友人などを一度棚卸しをして、人生100年ライフに備えるべきだと新たに思い直している次第。
以上が前作のポイントだ。
★
さて、最新刊『LIFE SHIFT 2 』~100年時代の行動戦略~では、どう進化した論説が語られているのだろうか?
著者は、~100年時代の行動戦略~を執筆する上で、数々の取材を重ねた結果、誰もが行動に移せるように「3つの要素」を掲げて自問自答をするように促している。問いは、いずれも人間の本質に根差したものだ。
では、人間としての可能性を開花させる「3つの要素」を挙げてみる。
① 物語・・・自分の人生のストーリーを紡ぎ、そのストーリーの道すじを歩むこと。それは、人生の意味を与え、人生で様々な選択を行う際の手引きとなるようなストーリーでなければならない。
物語を紡ぐための自己問答→「わたしはどのような仕事に就くのか?」「そのためにどのようなスキルが必要になるのか?」「どのようなキャリアを築くのか?」「老いるとはどのような経験なのか?」
まず、これらの問いに自問自答してみよう。
② 探索・・・学習をしながら自らの変身を重ねることで、人生で避けて通れない移行のプロセスを成功させる。
ここでも自問自答の用意がある→「長寿化によりキャリアの選択肢が広がるか?どのように選択肢を検討するのか?」「そのために必要なスキルは、どのようにして身に着けるのか?」「どのような変化を試みて、これまでより多くの移行を経験する人生をどうやって歩んでいくのか?」などだ。
少々、自分の奥深いところに踏み込んだ自問自答となるだろう。
③ 関係・・・深い絆をはぐくみ、有意義な人間関係を構築して維持すること。
ここでの自問自答はこうだ→「家庭のあり方が変わりつつある状況に、どのように対処するのか?」「子どもの数が減り、高齢者の数が多くなる世界は、どのようなものになるのか?」「世代間の調和を実現するために、わたしたちは何ができるのか?」などだ。
「3つの要点」を自問自答をしながら、自分の人生の主役として演じ切るために深く思考してみよう!という行動提案となっている。
どう?
意外と簡単かしら?
それとも、人生の「物語」は自分で考えるのか?!と改めて新鮮な驚きに満ちた人もいるだろう。
わたしも自問自答しながら、これから迎える第三の「人生」への挑戦を始めた。
そもそも、人生の道を自分で思い描き、その通りに歩めればこれこそが大成功の人生となるハズ。
しかし、わたし達は心のどこかで、「自分で考える人生なんて!恐れ多い」「誰でも簡単に歩める人生であればいい」と、安定と安泰ばかり求めてはいないだろうか?
この、自己保身を今、脱ぎ捨てて人生100年時代に向けて踏み出そう!という提案だ。
「100年も生きるのだから」不安なら、不安の根っこに勇気を持って対峙しよう。
「100年も生きるのだから」夢中になれないなら、夢中だった頃の自分を思いだそう。
とにかく、わたし達は確実に人生100年時代を生きるのだから。
思考は最高の友だちよ(笑)
※『LIFE SHIFT』100年時代の人生戦略 『LIFE SHIFT2』100年時代の行動戦略